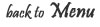Swing Girlsは、なぜSwing Girlsなのか?
思えば、映画館で上映されていた時、もっと言うと制作段階から「これは観るべき」と思っていた割に、結局DVDが発売され、さらに半年近く経ってから観たわけですけれど。
実際観てみると、「笑わせよう」という仕掛けが思ったより多いかな、という点以外はまぁ予想通りの作品でした。ええ話ですよね。青春ですよね。
ところで、「スウィング・ガールズ」はなぜ「スウィング・ガールズ」だったのでしょうか?「吹奏楽には足んねえけんど、ビッグバンドなら今居るメンバーでやれっから」
「でもよぅ〜、ジャズっておっさんのやるもんだべぇ?」
「インテリ面した客がブランデーグラスなんか回してよぉ〜(笑)」
「もっと格好いいのぁねんの?」
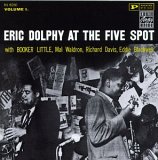
また、竹中直人演ずる教師がやっつけのフリージャズを吹いてみせたり、ジャズの精神論を語ってみせるシーンがある。彼はここで、演奏する喜びを知らない頭でっかちなリスナーとして戯画化されている。ここで、象徴的にとりあげられているのが Eric Dolphy At the Five Spotであるのは、偶然ではあるまい。
スウィング・ガールズでは、「即興演奏=improvisation」という、ジャズにおいて重要な要素に関しては注意深くオミットされている。その代わりに、この映画で徹底して力点が置かれているのは、ジャズの持つフィジカル面である。リズム、ノリ、グルーヴ感。即興性・抽象性はむしろ「頭でっかち」で陰鬱なものとして祝祭的な主人公との対立項として描かれ、揶揄の対象としてのみ存在し、掘り下げられることはない。
そして、それこそが「スウィング」ガールズという表題の真意ではないかと思うのである。つまりこの映画で語られているのは、やはりジャズではなくスウィング、なのである。
ジャズとスウィングは厳密に言うと違う。スウィングはジャズの中でのリズム形態の一つ、サブカテゴリーに過ぎない。
ジャズの揺籃期はニューオリンズやシカゴでの飲み屋もしくは娼館にて演奏された黒人音楽であった(正確にいうとクレオール音楽)。これらの音楽はあくまでBGMやダンス音楽として消費されるために存在していた。サブカルチャーという言葉のまだなかった時代、メインストリーム・カルチャー以外の文化は、単に消耗品として消費されるだけである。客の大半が白人であっても演奏者の殆どは黒人であり、彼等は店の従業員という立場と同じで、裏口から入場し裏口から帰っていくような日陰者の存在であった。つまりは日本の芸者などと同じ扱いだったわけだね。(※1)
飲み屋の日陰音楽だからって、本邦の芸者演奏とは規模が違うのはさすがアメリカで、高級なキャバレーやダンスホールでは上流階級の娯楽のためにはそうした楽団が恒常的に必要だったため、デューク・エリントンやルイ・アームストロングなどは10人前後、時にはそれ以上の編成のバンドを率いて活動をしていた。フォーマルな場であるから演奏するときの服装は当然正装であるが、扱いとしてはやはり使用人並の一段低い立場であった。
ところが、白人がビッグバンドを作った時に、状況は一変した。そう、ベニー・グッドマンがデビューしたとき、音楽的には黒人のバンドの延長線上にあったのに、白人の批評家は彼を「King of Swing」と評し、あたかも新しい芸術形態を白人が発明したかのような扱いをしたのだ!そしてベニーグッドマン以降、こうしたビッグバンドによる演奏が定番のフォーマットとなり、時期的にラジオまたレコードの普及と重なっていたため、爆発的にダンス音楽として流行した。1930年代のこれらのジャズの様式を、「スウィング」と言うわけです。
ベニーグッドマンは演奏者として白人黒人の区別をしなかったが、その受け手の方はそうではなかった。ベニーグッドマンが出現して初めて、メディアは「アメリカ文化」としてこのスウィングを取り扱い始めたのである。つまりは、ルーツである黒人を意図的に過小評価してベニーグッドマンやグレンミラーをメディアは持ち上げた。ジャズ/スウィングというものがまがりなりにも芸術として一般に認知されたのもこの頃。
で、ジャズの偉大な巨人であるルイ・アームストロングとデューク・エリントンはベニー・グッドマンよりも以前から精力的に活動していたし、スウィングという言葉が流行る前から同じような音楽をやっていたにもかかわらず、ベニー・グッドマンが創始者のように華やかに取りあげられていたわけで、当然面白いはずがない。
デューク・エリントンは、こうした状態を評して、(スウィングは商売に過ぎないが、ジャズは音楽だ)
大事なのは、スウィングという音楽はあくまでダンス音楽として普及したという事実である。
※1 もちろん当初からジャズの革新性に目をつけていた一部の批評家は居るわけですが、大衆的に認知されたのには、ベニーグッドマンの出現が大きなきっかけになっていたのは間違いあるまい。なにしろカーネギーホールで初めてジャズが演奏されたのはベニー・グッドマンが初めてなのだ。
ところで、日本でのジャズのイメージというと、ジャズ喫茶でかかっている「ビ・バップ」以降の印象が強い。
その最大の理由は、日本においてはジャズが普及したのが敗戦後のアメリカ軍占領時代以後であるからだと※2思われる。
日本のジャズは、スウィングからバップの過渡期に伝わった。そして50年代にアメリカが「輝けるアメリカ」として世界に君臨していた頃に、アメリカのイコンとしてもてはやされた。黒人公民権運動と安保闘争ね、ちょうどコルトレーンの活躍していた時代に最高潮を迎えるわけです。
つまり、日本で認識されているジャズというものは20世紀のジャズの歴史でいえば後半部分からで、スウィング時代がすっぽり抜け落ちている。
で、スウィング時代とそれ以後の決定的な違いというと、踊りを伴うかどうかということ。スウィングは踊りを前提として演奏されるが、40年代から発達したビバップは、これはリズム的に踊れないものであった。当時のビバップを演奏している店の注意書きに「座ってお聴き下さい」と書かれている写真が残されていたりする。バップ以降はジャズは座って鑑賞する音楽に転換したのである。
ま、これはある意味ジャズという音楽が音楽単体でも楽しむことのできる芸術に昇華したためだと言えなくもないのだが、皮肉なことにこれ以降のジャズって、実は日本で思われているほどはアメリカで流行っていない。なぜなら 踊れない=使えない、から。
しかし「遅れて編入してきた」日本のジャズ観では、スウィング時代はすっぽり抜け落ちているわけで、そもそも「ダンス音楽」としてのバックグラウンドを失って日本に根付くことを余儀なくされた。
日本で語られるジャズには身体性の観点がすっぽり抜け落ちていることが多く、ジャズの持っているいろいろな属性の中でもimprovisation=即興演奏がとりわけ偏重されがちな傾向があるのはおそらくこのためだ。快楽音楽という大前提があってこそ、50年代から60年代のジャズがストイシズムに傾倒した流れが生きてくるのだと思うのだけれど、日本ではストイシズムだけが過剰にクローズアップされてしまった。
で、話を戻しますけど、スウィング・ガールズは、こうしたことを踏まえてみると、まぎれもなく、スウィングなわけです。ジャズじゃなく。
この映画はそういう意味で日本におけるジャズ観に対するアンチテーゼとなりうるのではないか※3と思った。確かに「スウィング」というのはジャズの中では一部分に過ぎない、どころか「黒人文化」としてジャズをみた際には主導権を取りあげられていた負の歴史の音楽ではあるが、スウィングは、単純に楽しい。ジャズとは楽しいもの、楽しむべきものであるという永らく忘れ去られていたテーゼが、これをきっかけに日本でも根付けばいいと思います。
※2もちろん太平洋戦争直前や上海租界などでは伝わっていたが、いわゆる大衆芸術として一般性を獲得するのはまぎれもなく終戦後であろう。 また、どの時代が最もジャズが流行ったかという話は、世代間差があるので議論の決着をみることはないだろう。どの時代のマイルスが一番優れているかという議論にも似て、不毛である。
※3もっと言うと、団塊の世代史観的ジャズに対するアンチテーゼなのかもしれない
ここまでは、「スウィング」という言葉についての意味論。
ところで、もう一点僕が気になったのはドラマの筋についてであります。
この映画は、吹奏楽部が野球の応援に行く時の弁当を主人公らが届けるところから始まっているわけだが、炎天下に弁当を放って道草したことで、弁当が腐敗し、吹奏楽部員達がダウンすることが、主人公が楽器を始めるきっかけになっている。
主人公達は一貫して「アホの子」的な描写で描かれているのでこうした行為は「うっかり」「ドジ」のレベルで片づけられているが、純真無垢な主人公達があっけらかんと侵す過失としては、犯罪すれすれだよな、と思ったりもします。
物語世界での因果応報律を適用するなら、こうした行為はストーリーの中で代償されなければならない、つまりプロットの中で懲罰的なエピソードが後半に用意されたりとか、もしくは「借り」を返す場面が必要ではないかと思うのですが、このエピソードは、そのまま放り出されているようだ。どうも、そのせいで映画全体の調子がラテン気質な感じになっているきらいがある。
いいのか、ドラマツルギー的には、これで?