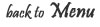Gerry Mulligun考
高校生から大学一年から二年生の頃にかけて、なぜかGerry Mulligunが好きな時期があった。
僕はトロンボーンなので、一緒にやっているBob brookmeyerとか、トランペットのChet Bakerだとかを主に聴いていたのだけれど、あの頃の僕は、ウエスト・コースト・ジャズが共通してもっている雰囲気に憧れていたのだと今となっては確かに思う。
ウエストコースト・ジャズは、音楽に必要以上に入れ込んだり、発狂するほどの自己表現を求めたりしない。もちろん、ウエスコトコーストの奏者達が、自らそういったコンセプトのもとに作り上げたのではないことはわかるのであるが、枠からはみ出そうとする熱意は、東海岸のそれと比べるといささか希薄なように思える。そういった「熱さ」とは無縁な大人な雰囲気、そういうものが、結果ある種ダンディズムのように映ったのかもしれない。それは逆に、悪くいえば屈託のなさや軽薄さに繋がるという危険も孕んでいるのだけれど。
マリガンのソロも驚くほど軽い。ゆらゆら木の葉の様によく揺れ、息が入っている間は必ずフレーズが回っている。ブロウアウトすることなど絶対にない。だけど、よく考えると楽器はバリトンサックスである。鈍重な楽器で、取り回しに難のある難しい楽器である。不思議だ。ダンプカーがジムカーナのコースをくるくると回っているような印象がある。
熱に浮かされている時に聴くGerry Mulligunは、なんだか床が揺れている様な、背中に響く様な妙な不安定感がある。聴くにつれ、不思議な感覚がある。
東海岸のハードバップなどは、むしろ射精に至る、絶頂感を期待して演奏しているのに対して、ウエスト・コーストは、むしろ射精を我慢する過程に重きをおいた音楽なのかな、と、思ったりもした。ウエストコースト・ジャズは射精「まで」の音楽なのだ。
あるいは熱で勃たなかったから、そういう感慨を抱いただけなのかもしれない。
(Apr, 2004初稿)