新規サイト011のヘッダー
前田勉 「窓枠大の空」
エッセイ・他
十田撓子 詩集『銘度利加』 〜 時空を超えて生を遺す 〜 詩誌「密造者」第101号掲載 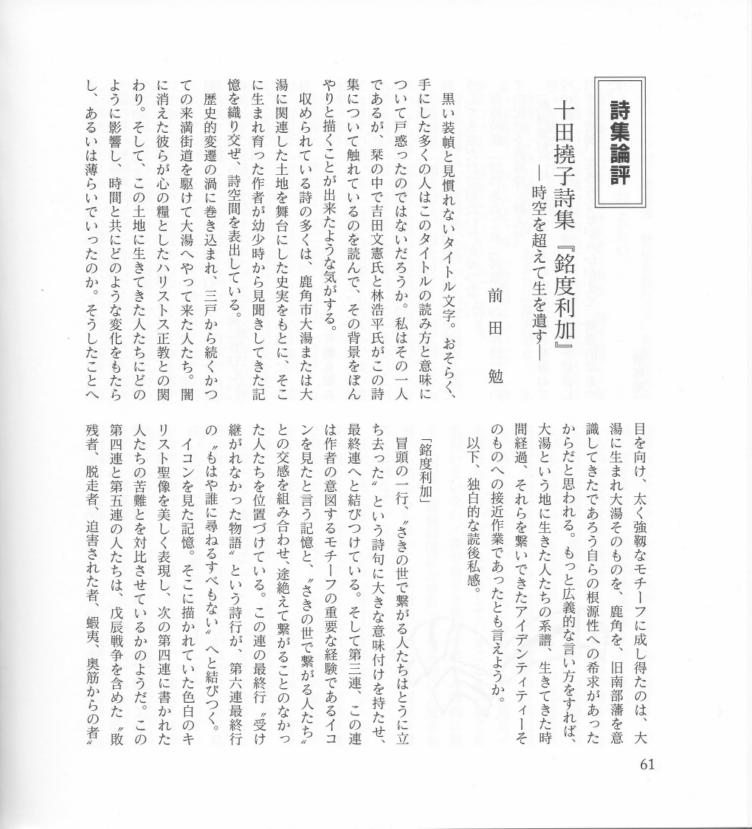 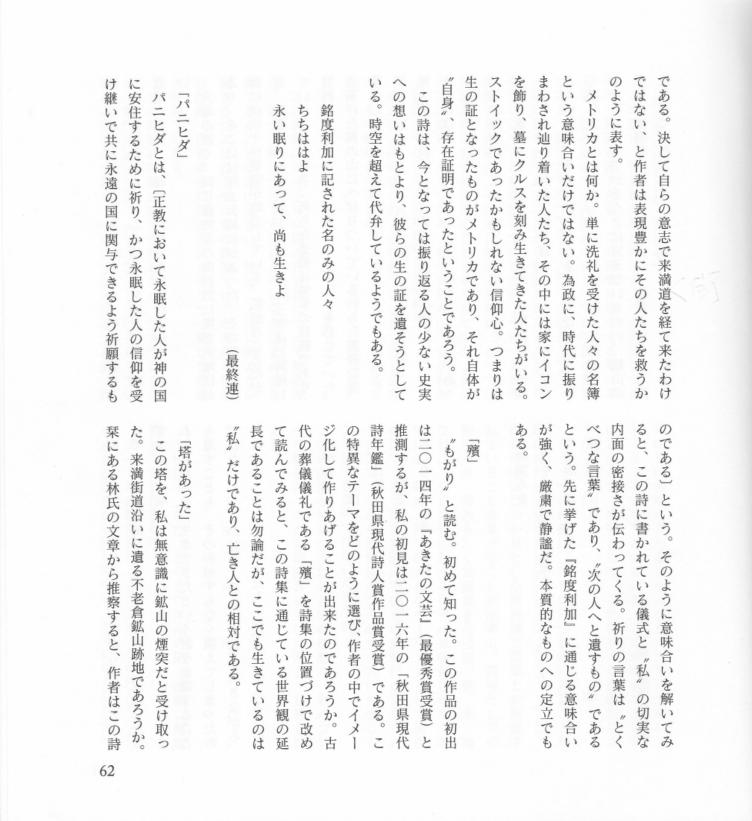 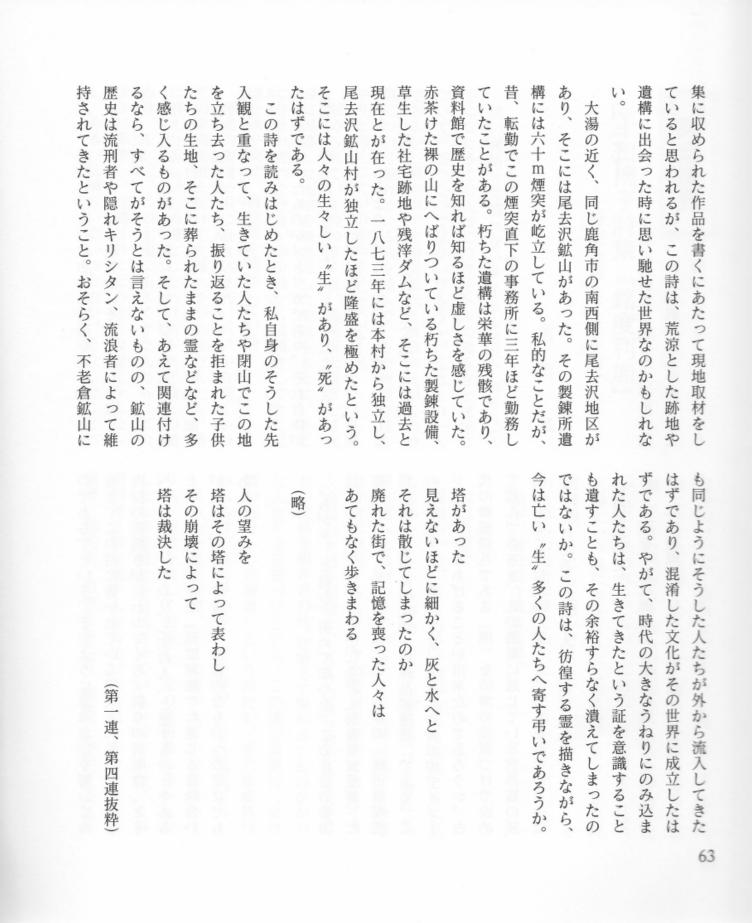 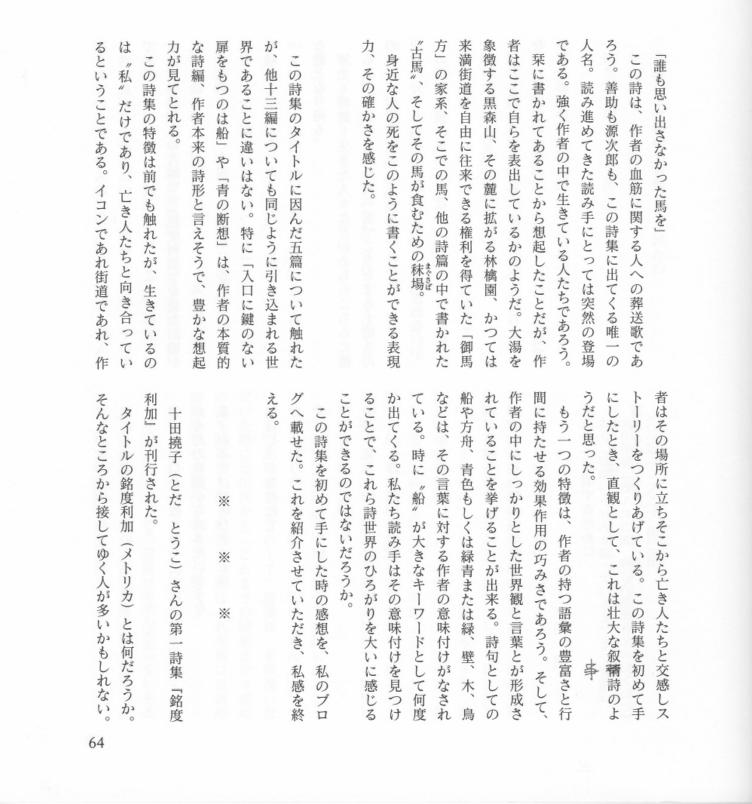 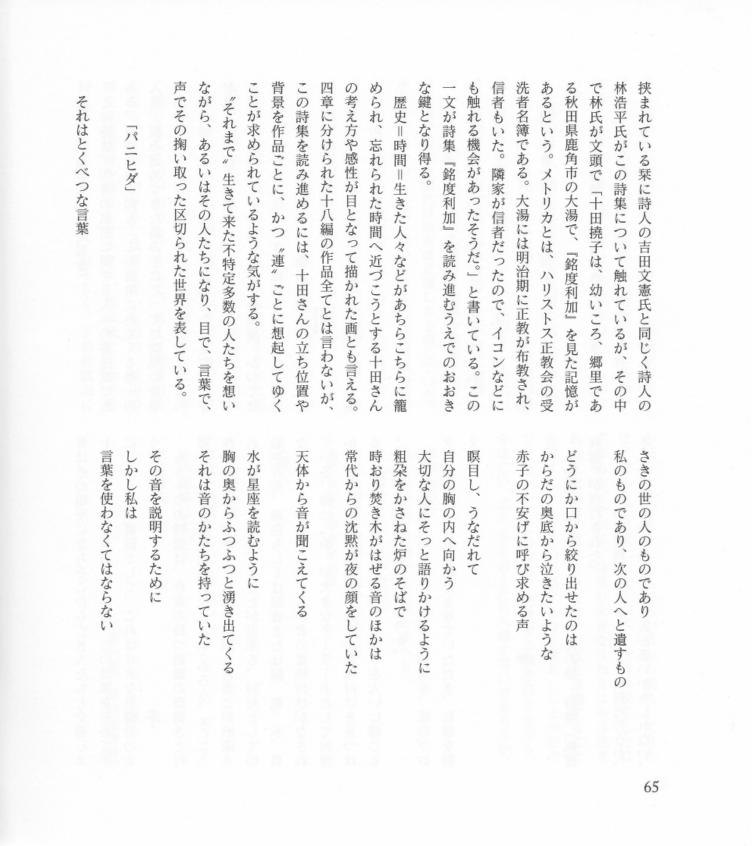 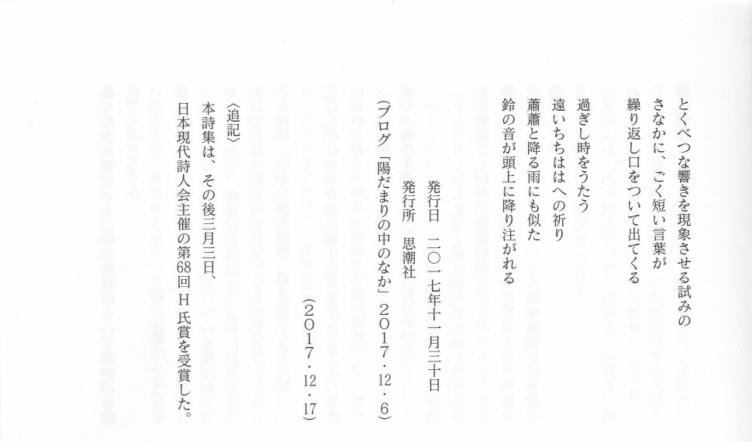 福司 満 詩集『友ぁ何処サ行った』 〜 方言詩から感じること 〜 詩誌「密造者」第99号掲載 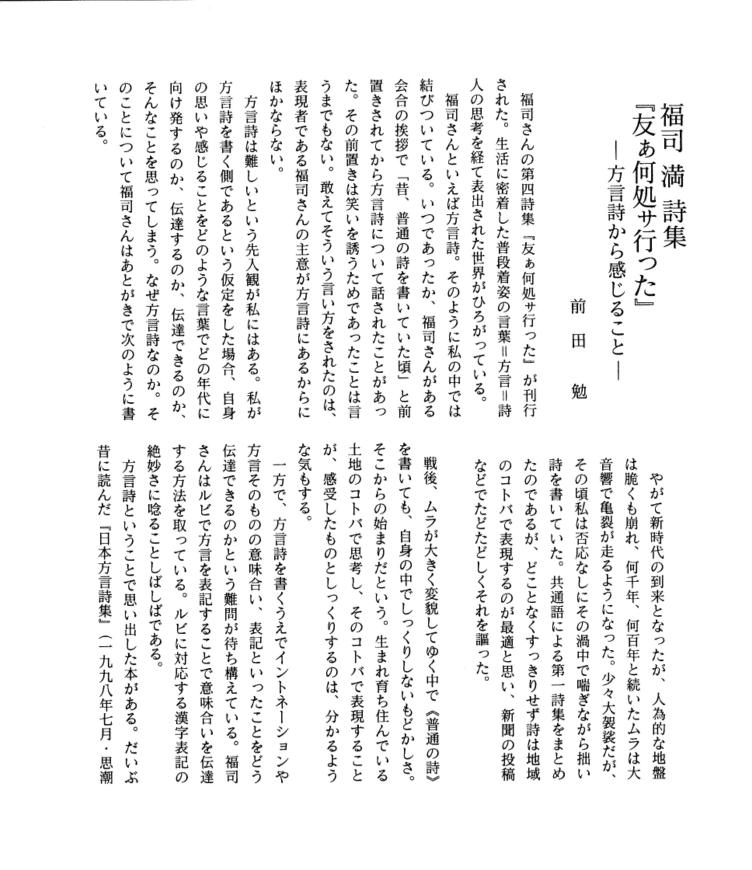 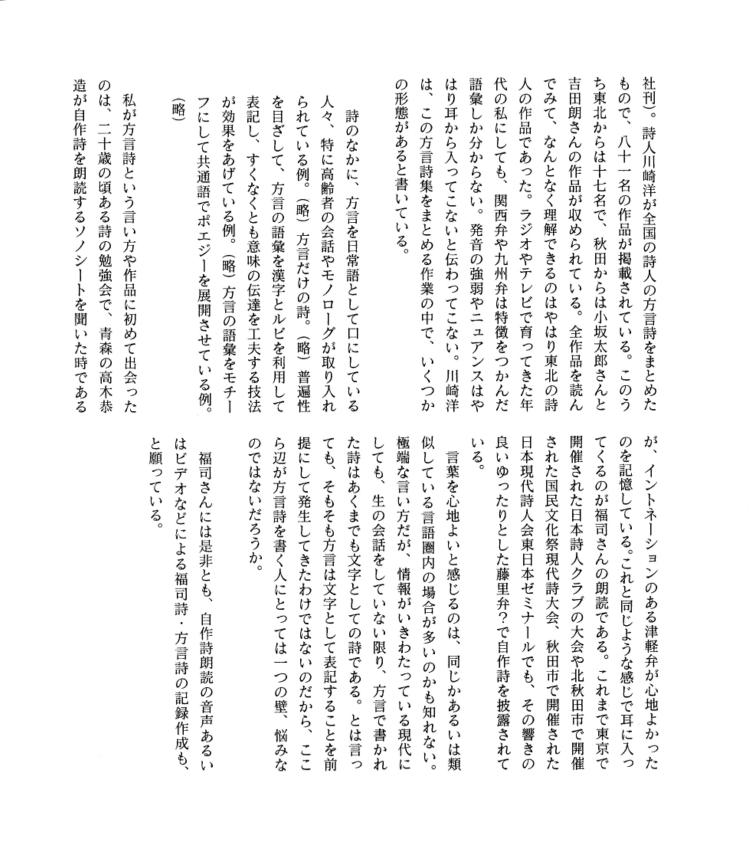 保坂英世詩画集「かがり火」を読んで 詩誌「密造者」第98号掲載 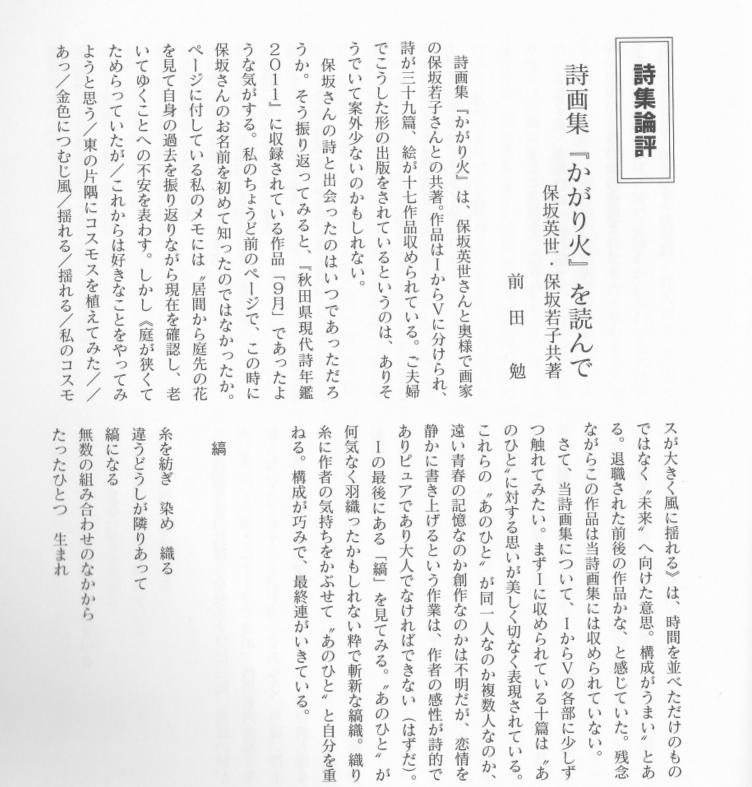 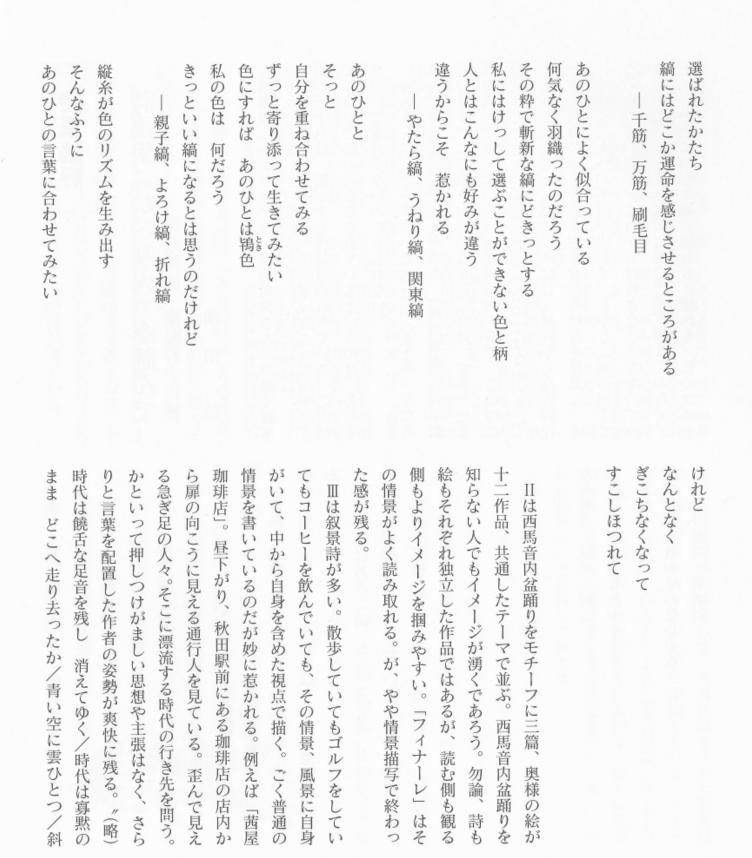 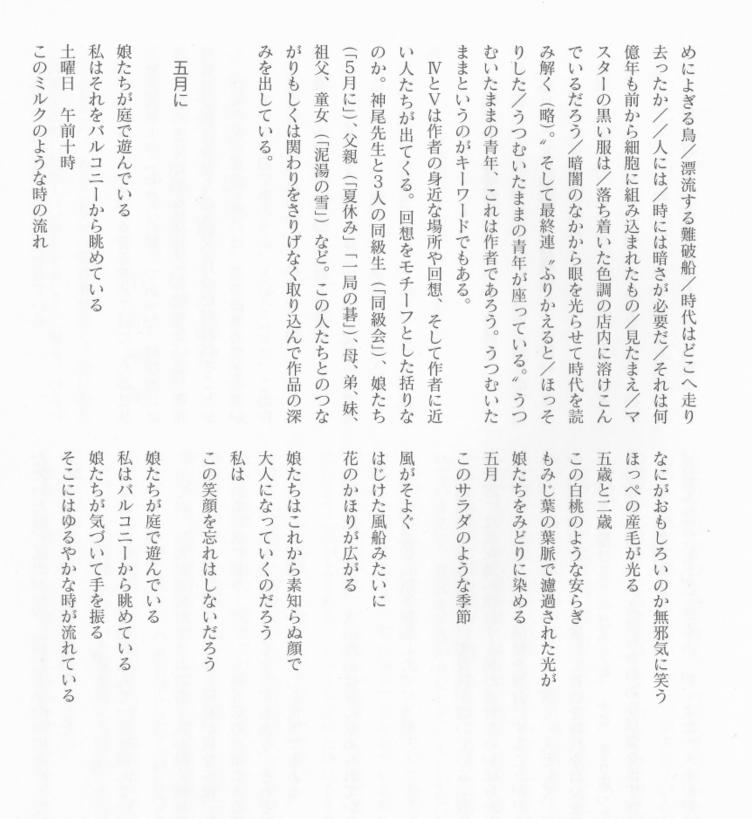 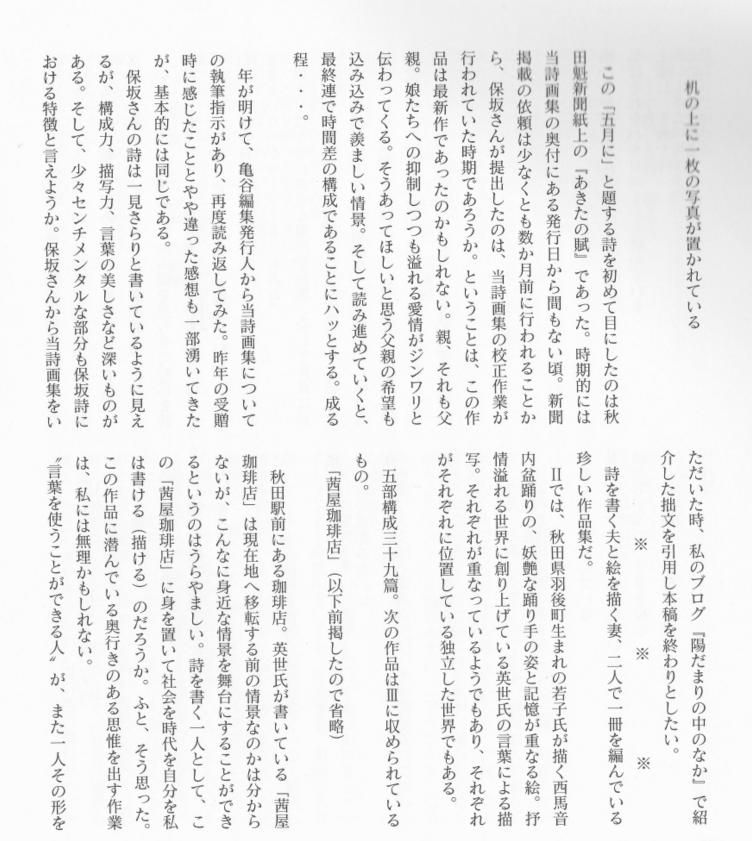  若木由紀夫・掌編集「ペルソナ」から感じるもの 詩誌「密造者」第96号掲載 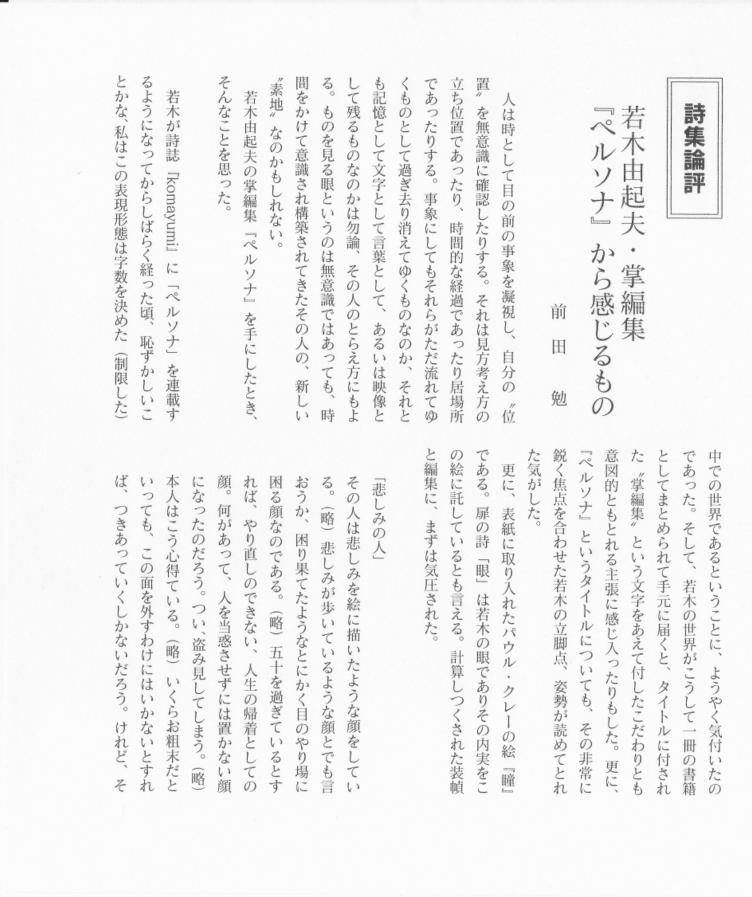  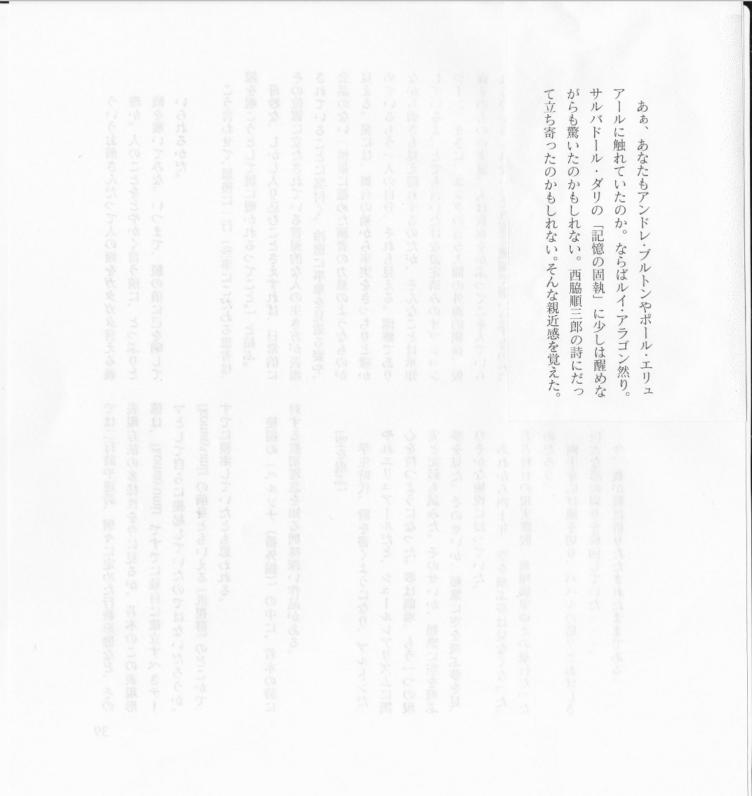 岡 三沙子 エッセイ集「寡黙な兄のハーモニカ」 「コールサック」第88号掲載 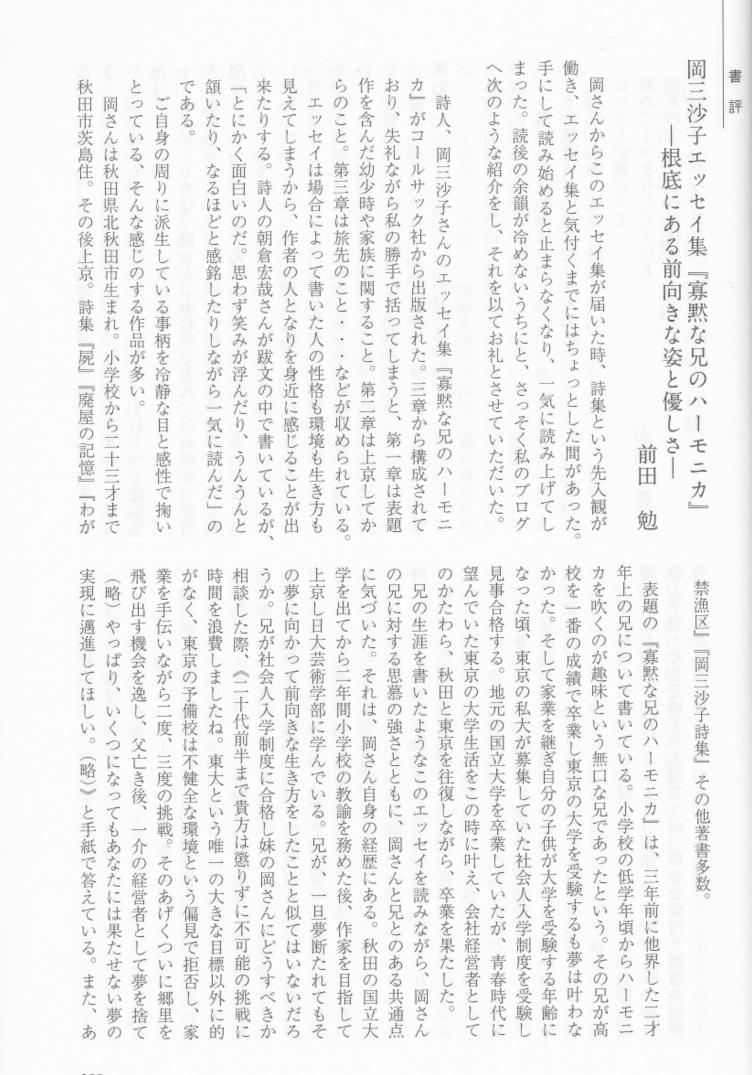 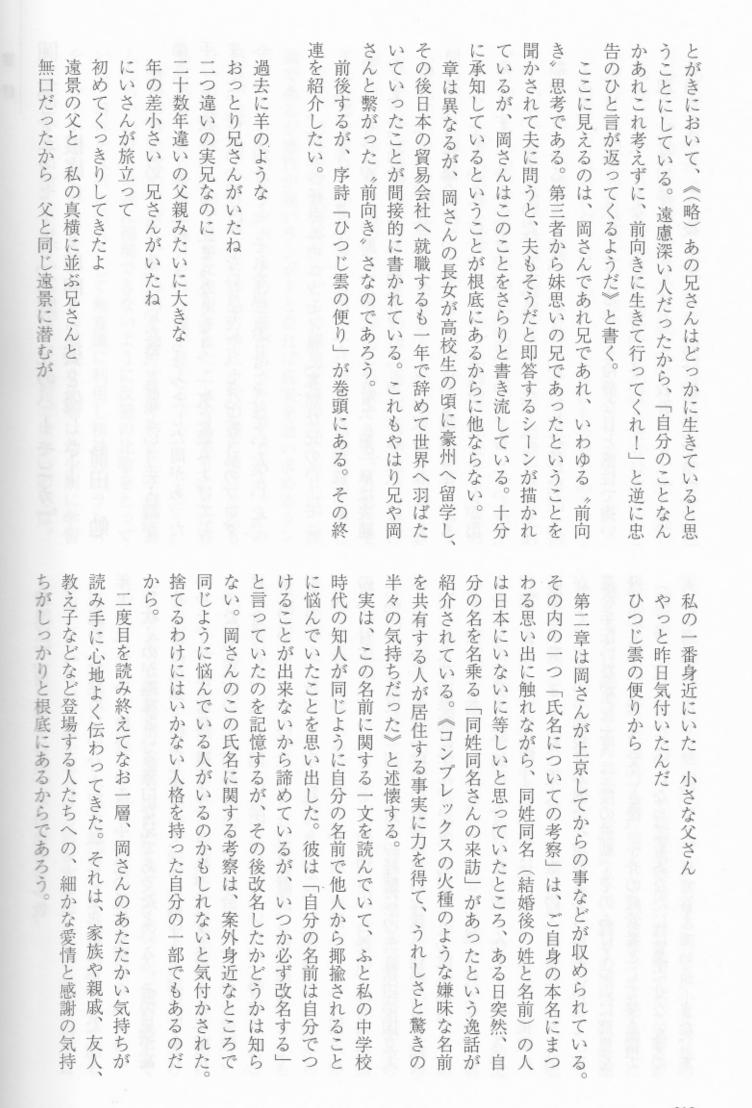 矢代レイ 詩集「水を生ける」 詩誌「密造者」第94号掲載 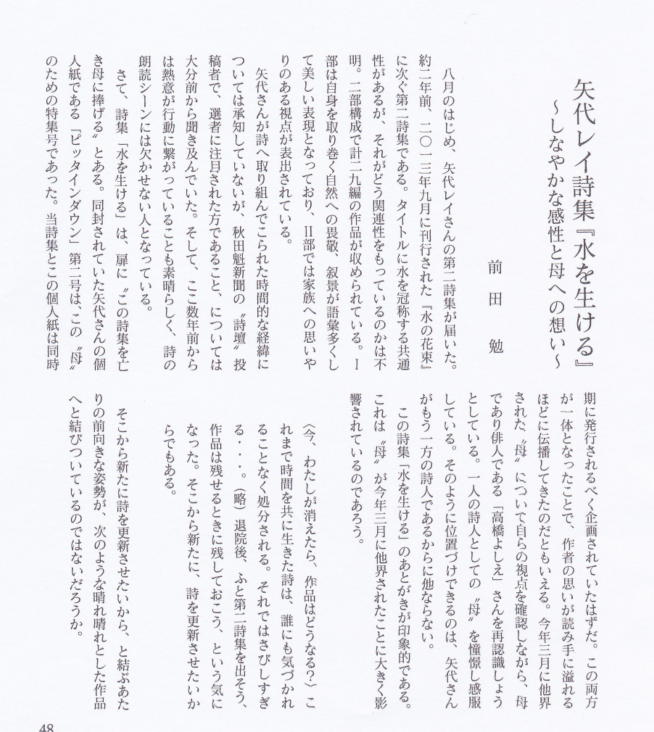 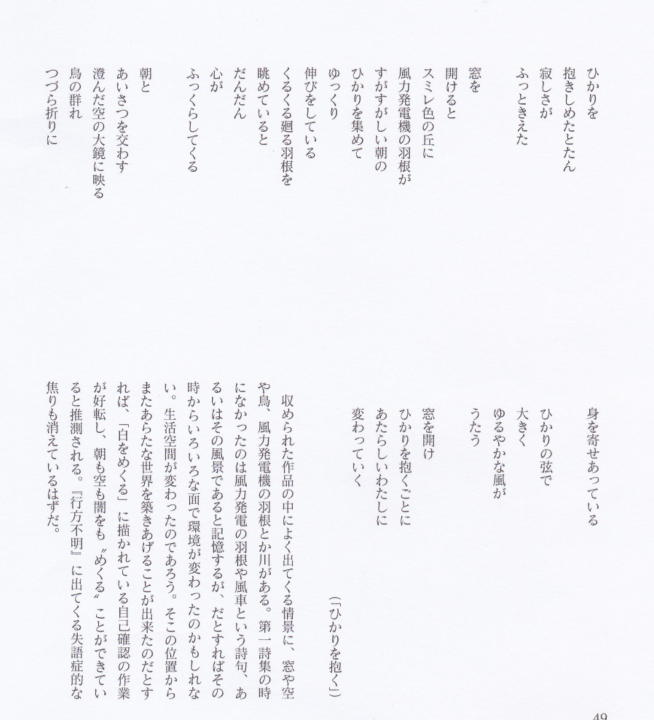 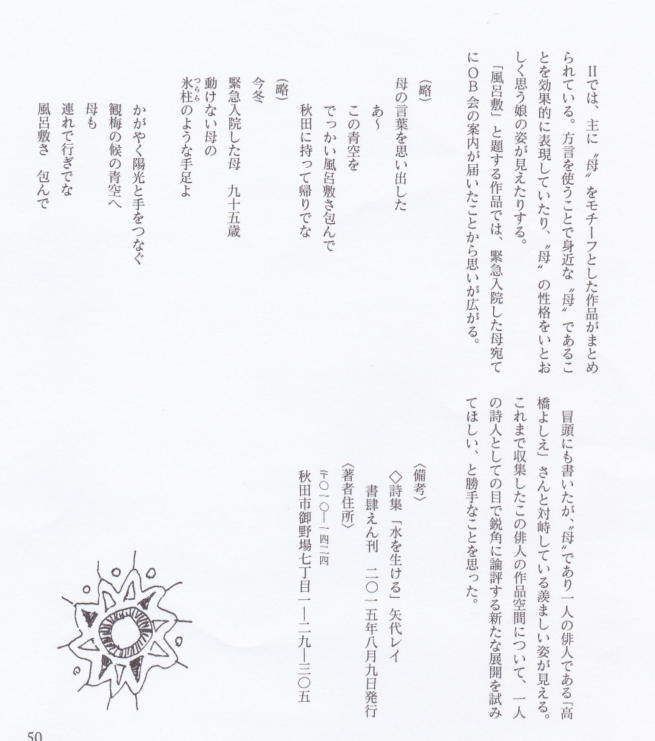 井野口彗子 詩集「火の文字」 昨年八月に上梓された井野口慧子さんの第八詩集。 一年前の詩集ではあるが、いいものは時間を問わず評価されるべきである、との亀谷編集発行人の意向により、私のところ へ届いた詩集である。あとがきを見ると、「木川陽子さんと三十六年続いた二人詩誌 『水声』も、彼女の他界で、二〇〇五 年十二月に終刊した」と記されている。実は、私が三十代前半の頃、広島の詩人、相良平八郎さんから「所用があって秋田 へ行くのでホテルで会おう」という連絡があり、そのころ所属していた詩誌の同人複数名と連れ立ってお会いしたことがあった。そ のことのつながりからであったかと思うが、同じ広島の詩人である木川陽子さんから詩誌『水声』が届いた。手元に残っているの は一九八五年十一月三十日発行の第九号しかないが、その『水声』のもう一人の同人が、井野口慧子さんであった。 詩集『火の文字』を読んでの第一印象は、言葉の確かさと丁寧さ、豊富な語彙、そして対象をしっかりと定めて書いている こと。読んでいると、湧き出すように連なる言葉が気持ちよくイメージされてくる。ⅠからⅤまで分けられた五十一編の作品を何 回か読んだ。多くとは言わないが、生と死がテーマになっている作品が目立つように感じた。それは父であり姑であり友人や知人 であり、広島の歴史。そして、井野口さんの子供であろうか。深い悲しみを硬質に表現することで、単なる感情ではないとでも 言っているようである。硬質な抒情とでも言ったらいいのだろうか。 その静かな源へ 夜明けになると 魂は 海から還ってきた 七つ星の柄杓で 汲みあげた 水滴の匂いが かすかにする
行ってきたのだ・・・ 急速に 大地を淀ませていく人間の 欲望の残骸を かい潜り 危うい日々のくらしの透き間から ふっと 耳や肩に届いてくる あの まなざしが 始まる方へ 変わりやすい人と人との 糸を伝って 零れてくる 懐かし気配が やってくる方へ
先に肉体を脱ぎ捨てていった者を 守護神とし 胸の磁針を揺らす合図に導かれて 千の夜の森を 彷徨する
鳥の声 川の音 花の記憶を
月は アンモナイトの螺環をちぎれた翅で 時間の網を砂に記す ゆっくり 巡り続けている めまいがするほどの 幾つもの生と死が とぎれがちな か細い光の線を つなげていく 痩せたあばら骨が きりきりと痛い 日毎に 衰えていく翼を 風に託しながら 薄い影を曳いていく 辿り着きたいのだ はるかに遠く遠く 阿野まなざしが生まれる所へ 見るものと 見られるものが 見たものと 見えなかったものが 宿命と運命が 喜びと悲しみが ひとつにとけ合って 輝いている その静かな源へ 井野口さんの詩を読んでいると、妙な言い方だが、生を考えるということは死を、死を考えるということは生を考えることである と思った。 この詩集に所収されている詩編から見るもう一つの特徴は、絵や染め物といった個展に対して、あるいは、亡くなった詩人や
画家に対して、とする副題を持つ作品が多いこと。一般的にも、こうした個人に対する作品はよくある。親しい人との接点とか美 術に関する感性があるからこそ表現可能ではあるが、読み手である私と詩に表現された人物とはこの時が初対面である。例え ばこの詩集の中に「氷解 父に」という作品がある。あるいは「姑」という作品がある。二作とも完成度の高い散文詩であるが、 (その表現形態はともかくとして)面識がなくても詩を書いた作者と親子であるという普遍性において、内容を解することも表現さ れたことへの近接も可能である。しかし、私がこれまでそうした書き方をすること少ないせいかもしれないが、詩集として見たとき、 少しばかりの違和感を持ったのは事実である。 ともあれ、詩集『火の文字』に表出されているものは、愛、生命、自然、社会であり、自らが苦悩しそれを越えてきた生のメッ
セージである。そうしたものが井野口さんの詩座であることがよく読み取ることが出来る。そして、詩句が、特に感覚的ともいえる 詩句が美しいことを述べておきたい。読んでいて意味としてというよりも感覚として入り込んでくることが気持ちよかった。最後に、 次の作品を紹介したい。 宙の奇蹟 枝々をひきちぎられて 咲くこできない花たち 苦い夏を耐えて 舞い積もった 記憶の葉っぱ
ちりばめられた 赤い実の日々 すべての残り香が 染みこんでいる 土の道は 微熱が続く あなたには みえるだろうか 真冬の陽の沈黙の中で 虹の花びら一輪微笑んでいる この宙の奇蹟 詩誌「密造者」第91号掲載 見上司 詩集 「一遇」 上司さんが、第三詩集『一遇』を出版された。 読み始めての第一印象は、「透明感」であり「誠実さ」であった。透明感とか誠実さとか言ったところで曖昧すぎて伝わりにくいと は 思うが、印象で言えばそうなる。なんとも爽やかで、明るくてアットホームで、人生観があって、読んでいるとニヤリとしたりホロリと してしまう情景、フレーズも配置されている。 この詩集を読み進んでいくと、これまでこのように思えた詩集は初めてだと気付いた。勿論、私の少ない読書量からすれば比較 対象が限られるが、読後このように感じたのは新鮮であった。そして、少なくとも私には表現できない、もしくは表現しにくい世界で あると思った。それは、率直に言って、詩語として発するにふさわしい年齢とか時期の違いだと思ったのだが、果たしてそうなのかどう かは自信が無い。 ともかく、見上さんの目線の優しさや話し言葉に近い書き方の表現が美しく表れていることに注視したい。
声にはまだ人間の不可知の不思議な力が宿っているのではないかと思う。 (略) それは、口に出せば、瞬時に消える光の粒々みたいなもので、何の痕跡も残さず、宙に霧散するばかりかもしれない。が、実は
そうではなく、聞く者の(自分自身を含めて)心に永遠に刻まれる何かである気がする。 だから、僕は、詩を、声に出すことを前提にして書いている。(略) と、あとがきにある。含蓄のある言葉だ。見上さんの詩の書き方、方法論としての根底が見える。 詩趣『一遇』は五章に分かれている。第一章・一遇、第二章・やさしき墓標群、第三章・ジュリエット、第四章・二人、第五章・ 「ただいちど」で三六編を収録。第一章・一遇には七編が収められており、星座に関する内容をモチーフにしながら、人類や時間 や気付くことの思い、生命力などを若々しく描く。 未来に ふいに -火星大接近の夜- (もしかすると 遠い昔に滅び去った火星の文明を 地球人類は忘れてしまったのかもしれない) 燃え尽くばかり赤い星の光に ふとそんな気がした たとえば ぼくらが真冬の雲間に見るオリオンを アンデスの山狭や ケープタウンの港町では 真冬の星空に見るように ぼくらには常に見えている事実と 見えていない事実があり それどころか生涯かけてさえも知りえない 無数の事実がある 多分ぼくらはいつか忘れたり 気がつかずにいたりしてしまうんだろう 遠い日に受けた だれかからの 数え切れない優しさを 今見るあの星のまたたきが 数千万年前に放たれた光のベクトルであるように 遠い昔に忘れ去った大切な記憶が 未来にふいに思い出されるかもしれない 昨日放ったぼくの吐息や思いが 明日はあなたに届くかもしれない 火星大接近の夜、”遠い昔に滅び去った火星の文明を地球人類は忘れてしまっているかもしれない”と思ったと言い、”常に見 えている事実”と”見えていない事実”があることや、”それどころか生涯かけてさえも知りえない無数の事実がある”ことに気付く。 気付くことと気付かないことに”気付いた”とも言い得て、だからこそ、最後の二行が活きてくる。この詩で言おうとしていること、感じ たことに大きな意外性は含まれていないが、数千万年前の宇宙の話からはじまり、”昨日放った吐息や思い”が”明日届くかもし れない”と現実に戻るあたり、シンプルだが考えられた構成と言える。捉え方いろいろあるだろうが、これは”あなた”へ伝えるための 素敵なラブソングだ。”あなた”は読み手であってもいい。 第二章では虫や蛇や蛙などが出てくる。この中の「大蛙」は注視すべき作品だと思った。路傍に、ひっくり返って死んでいる蛙が” てらっと”光っていたということから始まるこの詩は、見上さんの触れて欲しくない心象部分であるのかもしれない。今風で言えばトラ ウマ的で思い出したくない何かとの接点なのかもしれない。自分自身。 なぜか、ひっくり返って死んでいる蛙に対して怒りを覚えている。”落ちていた”とする死体に。それが、次連では「異文」として、率 直な感情を追加表出させながら、少し異なる解釈で表している。まるで翻訳しているかのようだ。バージョン変えというスタイルでは たまに見かけるのでそうそう真新しいものではないが、この作品に合っていることや内容の濃さに惹かれた。とにかく思い出したくもな いそれを、あえて言葉として文字として表わして”しまった。”そんな本質に係わる吐露である。また、”てらっと”という表現や途中で 句読点を使用していること、更に”だぶだぶだぶ”と三回繰り返すことで泥水が脈打つように流れている情景が強調されていること など、表現技法の巧さがさらりと出されている作品でもある。揚羽蝶を配置する暗示的なあり方も心憎い。 大蛙 夏の終わりの真っ青な空を仰いで ひっくりかえった蛙の 死体が 朝の白い舗装道路に てらっと光って 落ちていた 私はゆえない 苦いような怒りをおぼえた にくにくしい、おろかな 黒いかれんな揚羽蝶がその上を 横切った 堤防の下に潟水はきたない泥色ににごり だぶだぶだぶと波打っていた。 異文 晴れ上がった晩夏の烈々とした蒼穹を仰いで ひっくり返った大蛙の死体が 朝の白い舗装道路のまん中に てらりと光って落ちていた (にくにくしいおろかな死体め!) 堤防の下に潟水は きたならしい泥色に濁りに濁り だぶだぶだぶと波打っていた 蔓草はいやらしく繁茂して にょろにょろとどうしようもなく 嫌な記憶のように地面を這って延びていた (おれの胸にしみついたあの思い出、 ああおれはもう駄目になってしまったと、 おれをさいなむあの無残な絶望の記憶。) 黒い可憐な揚羽蝶が 目の前の死体の上を 無常に横切り飛び去っていった。 付記 ああ、あれはどうしようもなく嫌な記憶の中で てらてらとおろかしくひっくり返っていた。 第三章から終わりの第五章までは、家族への愛が一杯盛り込まれた世界だ。そのはじまりが第3章の「シドニーの片隅で」、「か らっぽだった ぼくの部屋に・・・」、「ジュリエット」と続く。これらの作品を最初に配したのは、二人の生活のスタートだからであり、後 に登場してくる”天使たち”との係わりへと結びつけるためであろう。こんなにも家族に対してあたたかく心から思いを発している書き 手はめずらしい。表現も率直だ。今年(二〇一三年)五月、大潟村で開催された日本詩人クラブ秋田大会で見た、見上さんの、 メガネの奥で情熱的にきらきらしていた眼と一致する。全く違和感が無い。 見上さんは中学校の先生らしい。かといってそれがどうなのかということに言及したり妙な思い入れをしようとするつもりはない。た だ、多感な子供達と日々接していることが、何らかの作用として見上さんの世界に色濃く影響しているのかもしれないと思った。 見上司さんは思っていたとおりの、素敵な世界を書いていた。 寓話として それはどういう話だったか とうに忘れてしまったが、 お話好きの娘は いつもお話を読んでもらうのをせがんだ 素子て終わると こういった いいお話だったね 物語はとるにたりない動物たちの話で いや動物といいながら 彼らは喋ったり笑ったり ケンカしたり我がままして駄々をこねたりする つまりは人間世界の一つの縮図で いわゆる寓話であるのだが・・・ 人はいったい幾つの寓話をもっているのだろう 私たちは子どもらにいったい幾つの寓話を 話して聞かせることができるのだろう また私たちの周りは無数の寓話で 満ちているような気がする 本当は人間世界は もっと聞くに堪えな 感情のいさかいがあり、義理のしがらみがあり 生活の泥濘がある 人はそれから逃れられない が、その中を生きていく知恵もあり、 打ち勝つ勇気もあり、 交し合う優しさがある 私たちは子どもたちに寓話として、 もっと語らなければならないのではないだろうか そしてそのたび こう言葉を交わすのだ いいお話だったね うん そうだね。 詩誌「密造者」第89号掲載 出版を祝う会の新しい形 なんとも趣のある、詩集出版を祝う会であった。
六月十九日、北秋田市上杉の「太平寺」において、『亀谷健樹さんの詩集「水を聴く」出をお祝いする集い』が開催された。 呼びかけ人からの案内文には『震災による自粛ムードもあって延び延びに』なっていたことが述べられ、『禅の境涯を言葉に表現
された貴重な詩集』であることから『その意味で会場をご本人の住処でもある、曹洞宗「太平寺」に設け』たとある。次第は第一 部「茶道へのいざない・お茶室、野点コース」、第二部「ミニ懐石による昼食」、第三部「野の花を自由に活ける楽しさ」第四部 「大震災物故者精霊供養会」、第五部「出版お祝いパーティー」と五部構成である。 訪れると、茶室脇の水琴窟に案内された。水琴窟はテレビやラジオでその音を耳にしたことがあったが、直接生でその音を聞く のは初めてであった。腰をかがめ地面から出ている筒に左耳を当てると、水滴の落ちた音が反響音となって心地よくひろがった。 静寂な湖水に投じられた小さな石ころ、そこから次々と展開するきめ細かな波紋が想起される。詩集のタイトルにし、そして水琴 窟を造り上げてしまった著者の思い入れが感じられた。 数年ぶりに抹茶を含み、散策し、奥様の手作り料理を交えた昼食を戴き、そして参加者がそれぞれに合った時間を過ごす。私 は外へ出て本堂のつくりを眺め、楼門を撮る。 本堂に戻ると、花器と花があり、参加者が思い思いに活けて大震災物故者精霊の供養に添えるのだという。一輪挿しに黄色
い花を挿した。思えば、花を活けたことはなかったので戸惑ったが、野の花を準備したという意味合いに感じるものがあり、季節の 色である黄色を無意識に選んだ。 外で梵鐘が撞かれ、そして住職と東堂である著者の読経が続く。参加者が一人ひとり焼香する。 詩集出版に関する祝意と参加者のコメント等はそのあと部屋を別にして行われたが、全体、なんとも趣のある出版を祝う会であ
った。勿論初めて経験する構成と内容で、こうした集いもまた好し。出版を祝う会の新しい形として興味深い。著者には失礼とは 思うが、私は私の中に潜り込んで、楽しく心ゆったりと過ごすことのできた日であった。 詩誌「密造者」第82号掲載 未だかつて有らず 三月十一日午後二時四十六分、マグニチュード八.八の巨大地震が発生した。
勤務先の事務所は揺れに揺れ、半信半疑の表情をした同僚達も、私も、動けずに居た。一瞬、日本海中部地震を思ったが、 あの時よりも長く、ゆったりとした横揺れは不気味であった。決して冷静ではなかったが、外への退避と各職場への連絡を指示し、 安全を確認した。幸い、人的被害はなかった。停電と同時にボイラ、ポンプ、モーター、熔解炉、パソコン、ファックス、電話機能の 一部などなど電力に依存する機械類が停止し、その確認に追われた。こうなるとほとんどの仕事は出来ず、いかにネットワークを整 備した事業所であっても何の役にも立たない。一方で、アナログ波のラジオは時間経過と共に太平洋側の被害が甚大であることを 伝えてきて、想像以上の災害であることが判明してゆく。 気付いたら二十二時をまわっていた。交代体制をとってひとまず宅し、自宅の現状を確認。変化は無いようだった。布団についた 頃、何回電話をかけてもつながらなかった仙台市若林区に住む息子とようやく連絡が取れた。生きていてくれたようだ。開口一番、 生きているのが奇跡だとボソリ。それから、近くの浜で二〇〇人もの死体がでたこと、街をはじめ会社の建物、社用トラック、マイカ ーが冠水したこと、同僚が車ごと流されて行方不明なことなどを語った。精神的にひどく疲れている様子であった。 震災発生から一週間が経ちガソリン給油が容易になった頃、物資を積んで仙台の息子のところへ出かけた。仙台北部自動車 道を境に東側の田圃には流れ着いたゴミが散在していた。遠くに見える海岸線まで二、三kmはあろうか。こんなにも遠くへ津波は 到達したのか。自動車道の堤体が津波を止めたのかもしれない。一般道へ下りると、流されてきたと思われる車が道路や家の脇、 屋根の上、橋げたの間などへ無残に”転がって”いた。大型トラックが仰向けになり、物流倉庫がコンクリートの基礎を空に向けて傾 き、広すぎる駐車場かと見まがうほど何も無い”生活空間”が広がっていた。港に近いあたりは通行禁止で警察官が警備していた。 遺体の捜索が続いているのだと息子が言う。言葉がないとはこのことか。ただただ沈黙。黙るしかない。いや、どう言葉を発すればい いのか分からないから閉ざすだけ。思考が止まった。 日を追うごとに死者や行方不明者の数が増え、生活機能が停止していることが判明してきた頃、ようやく少しだけ救援の物流が 動き出した。勤務先の関係では岩手、宮城、福島、茨城などに在る事業所が被災したが、幸いなことに人的被害は無かった。西 日本にある事業所から被害のほとんど無かった秋田に救援物資が一旦届き、それを被災した隣県事業所へ再発送する作業を行 った。何もかもが”訓練”ではないことを実感しながら、持ち場立場からみんなが懸命に動いた。 報道は未曾有の大震災だと報じる。昔、勤務先の広報誌を担当していたことがあった。一九八三年の日本海中部地震が発生 した時、私は記事のサブタイトルに未曾有という言葉を使用した。その歳までに経験した地震の中で、最大のものであったからたが、 当時、公務員で広報を担当していた友人のHは、その言葉は今回の地震では相応しくないと言った。もっと重いものだと言う。その 後、一九九五年の阪神・淡路大震災が発生した時、煙が立ち上がり高速道路が倒れているTV中継を見て、これが未曾有なの だと実感したものだが、今回はそれ以上、まさに「未(いま)だ嘗(かつ)て有(あら)ず」そのものである。 震災で亡くなられた方々のご冥福をお祈りいたしますと共に、被災された皆様に心よりお見舞い申し上げます。 詩誌「密造者」第81号掲載 吉沢悦郎 詩集『インサイド ストーリー』
〜緻密さと感情表出の巧さ〜 秋田県大仙市の詩人、吉沢悦郎さんが詩集『インサイド ストーリー』を出版された。
封書を開けて本詩集を目にした時からすでに”吉沢イズム”、いや、吉沢さんらしさが始まっていた。まずタイトル。第二詩集の『ア ウトサイドストーリー』を知っている人は同じことを思ったかも知れない。タイトルだけのことだが、私は思わずニヤリとしてしまった。特段 の意味は無い。意味は無いが吉沢さんらしいという思いが瞬時に想起された。そして次に、表紙に挟まれていた「本詩集を受けとっ てくださった方へ」との紙片。「まずもって勝手な献呈をお詫び」するという文面は、私が二十代初期に出会った頃の、気遣いのある、 ちょっとシャイで不良っぽい、そして直言できる数少ない詩人”吉沢悦郎”さんそのものであった。 『インサイド ストーリー』に収められた作品は十二編。読み進むと何度も繰り返される情景に出遭う。朝鮮半島の都市、京城。 黄金町、初音町・・・。勝手に大別してみると、著者の生地に関連した作品が六編ある。大きな意味合いを持つ六編であろう。後 ほど触れたい。 吉沢さんの詩の特徴は、造語するなら”思考詩”とでも言おうか。自身の世界をどんどん押し出して、時には時間経過を細切れ にしてゆく。読み手はその隠された感情や思考をどう紡いでいけるのか。読み手側にとっての”思考詩”である。 いずれにしても、言葉の大切さを熟知した表現力や豊富な語彙、そして感情表現にしろ情景描写にしろ、変に着飾らないコトバ遣 いが活きている。 タラス・ブーリバ 回想記(六) タラス・ブーリバとは何だろうか。そんな無知な読み手がいきなり迷った。吉沢さんの豊富な読書歴からすれば、『秋田県現代詩年 鑑2011』に掲載された『異聞・ペールギュント物語』のように、ちょっと異質な?文学作品(小説の)の主人公に意味合いを被せて いるのかもしれない・・・。そんなことから探し始めてようやくゴーゴリの小説、『隊長ブーリバ』であることに辿りついた。 南ロシアの正義感あるコサックの隊長ブーリバは、ロシア正教と対立するポーランド人と戦うが、参戦した彼の子供二人のうちの弟 が相手将軍の娘と恋に落ち・・・結局、父ブーリバは自らの手で息子を死に追いやる。一方、兄はポーランド軍に捕らえられ、息子 を救おうとして敵陣に忍び込んだブーリバの目の前で処刑されてしまう。父ブーリバは復讐の鬼となって戦いを続ける・・・・というストー リーのようだ。フランス映画にもなったという。 八歳の「僕」は「黄金座」で燃える隊長ブーリバを観た。ブーリバの恋人アンドリィは故国ウクライナを「我々の魂にとって何よりも恋し く懐かしいもの。(略)私の故国は貴方なのだ! 貴方の胸が私の故国なのだ!」と言う。そして吉沢さんは書く。 僕の見知らぬ故国は 内地という名のNIPPONで よく知っている母の地は 昨日の故国 ぼくが故国と呼ぶことを許されぬ地(略) 一九四五年九月、八歳の著者は自身の故国から午後四時の汽車に乗って出た。ずっとそれ以来「走っているのだ たぶん」、いま だに走っている。(生地を故国と呼ぶことを許されないまま、だ。同時に、母の故国日本へ走っているのだ)ブーリバと二人の子供の運 命、そして著者とその家族との関わりを巧みに織り込んで、「電鈴」の鳴り続ける駅舎を背にまだ走っている。まだ、走っているのだ。 異聞・ペールギュント物語 (秋田県現代詩人協会報第四十二号に掲載した、年鑑総括評をそのまま転載する) なんとも意味深な世界である。想像は読み手の勝手だから言及しないが、この作品に出てくるペールギュントはイプセンの詩劇の主 人公で、放浪・放蕩を繰り返す人物のことであろうか。冒頭で「女」に彼の名前を言わせ、そして最終連で「その時二十歳 アデンア ラビアなんて知りもしなかった」と言って終わる。実はここに吉沢さんの緻密な構成と効果の巧さ、ちよっとクールな姿が見える。敢えて言 えば、この最終連から実は始まりが展開していくのかもしれない。「僕は二十歳だった。それが人の一生で一番美しい年齢などと誰にも 言わせない。一歩足を踏みはずせば、いっさいが若者をだめにしてしまう」という『アランアラビア』の始まりの文面を知っていれば、この作 品をいかようにも読み取れるからである。タイトルに付した”異聞”とは吉沢さんの照れなのか。 帰郷 不思議な時間だ。うつつか、夢か。「僕」はとうとう「帰った 初音街54番地」。「僕」の原点。そこにいたのは時間を越えた祖母であ ると言う。時間経過を読むべきか。 昭和二十一年三月、家族旅行 家族旅行とは自虐的でシニカルな言い方ではなかったか。自身の「故国」から見知らぬ「故国」への引き揚げ。 魔から逃れるように窓は閉められ 汽車は在りし日の何処かをつっ走り 帰ったのだ。その間、「僕」は眠っていた。帰るまでのどこかの部分が欠落し空白であったとしても、「帰った」のだ。 昭和二十年八月十五日 -朝鮮京城で- 「アレガ重大放送ジャロウカ。」と言った祖母の独り言を六十五年記憶している「僕」は、その日のことを 昭和二十年八月十五日 朝鮮京城 僕のつぎの僕 がはじまることができた 真昼だった 刻まれた少年の心の傷は癒えることなくジュクジュクと化膿している、とその日を位置づけながらも原点に戻ろうとしているのが見えてく る。 結局、吉沢さんは原点へ戻ろうとしている。原点は何かと模索し続けていたに違いない。「つぎの僕」が始まった。
汽車はとうとう終着駅に来た 僕は駅舎を出 家路をたどる 彫像 のように静まり返っている十五夜の街 本町から黄金町 黄金町 から初音町へ 僕は無人の電車通りを急ぎに急ぐ 右折 どぶ川 に沿い山田鉄工所 左折 橋を渡る 綿屋の角は右に 帰ってはならぬ故郷である 許されない故郷である しかし とう とう僕は帰った 初音町54番地 (帰郷) このエリアが原点であろう。地区というよりは精神的な。帰ってはならぬ故郷と言うコトバの奥に隠れている意味合いは深いに違いな い。そこを書こうとして私はとどまった。ずるいかもしれないが、それを読み取ればいいのであって、こうだろう、と言う必要はない。読み手 は。直視する「僕」の経過そのものを感じ取ればいい。そう思った。 2011,06,26 ホタル
先日、長野市へ行く機会があり、ついでに鬼無里(きなさ)地区の古民家とホタルを見てきた。古民家とホタル、癒しを求め日本の 原風景を訪れる・・・・まるで某月刊誌の特集タイトルにでもなりそうだが、そんな大仰な思いではなく、ただホタルを見たかっただけで ある。 鬼無里地区の人の説明では、十数年にわたって環境整備に取り組んできた成果だという。ホタルの生態研究から始まり、集落の 生活排水の改善や田んぼへの農薬散布制限、河の掃除、繁茂する草木の適宜な刈り取りなど、ホタルの復活を願っての行動のよ うであった。そして、更に驚いたのは、ホタルが飛び出しやすいように街灯の光量や家からの光の漏れを最小限にするなど、この時期は 生活面においてもホタル優先だという。 暗くなると地元の人も集まってきて、それぞれ高台の田んぼの方に歩き出す。雨上がりなので飛んでいないかも知れないと言われて いたが、目が慣れてきたころ、あちらこちらから歓声が上がる。ふんわりと飛び交いながら柔らかくもしっかりとした光を放つホタルを次々 と見ることができた。光量のあるゲンジボタル、葉陰で小さめの光を放つヘイケボタル。説明があるからなお感心したりする。 ホタルを最後に見たのは20年くらい前になってしまっただろうか。子供達と散歩していた時に偶然、田んぼの畦の周りが光っているの を見つけたときがあった。今、そこは住宅地で、田んぼは更に遠くへ行かなとない。 秋田市では平成6年、11年、16年の3回「ホタルマップ」を作成している。市民からの情報に基づき市の環境部門の職員が調査 確認したもので、平成16年の秋田市内(合併前)でホタルを確認できた箇所は164箇所。平成11年に比べて市街地での数が減 っている。田んぼが少なくなり、小川はコンクリートで覆われ、あるいは汚れ、夜はスーパーマーケットやコンビニの明かりが煌々としている。 減るのは当たり前か。 ホタルの生息条件は①1年を通じて水が枯れなく流れている所②川岸が草に覆われ木陰である所③夜、川の周りが明るくない所 で川底に幼虫が隠れる小石などが点在している所、とある。自分の住む周りを見渡すとなかな難しい。 ホタルを20年ぶりに見て感動した。同時に、環境整備と保全と生活、口で言うほど簡単なことではないと思った。 詩誌「密造者」第76号掲載 帰りに一杯 仕事に関連して外で酒を飲む機会は時々あるが、自分から率先してということはほとんどない。家で机に向かってビールをグビグビや るに越したことはない。ながら族の典型的なパターンで長年過ごしてきた日課?だから、これはもう立派な「生活習慣病」である。ところ が、昨秋あたりから職場の先輩と帰り際に近くのラーメン屋へ立ち寄るようになった。私達はこの店で一度としてラーメンを食べたことはな く、酒ばかり飲んでは延々と山がどうの用具がどうのと登山の話をしながら、やがて、四方山話へと転じる。店の主人夫妻は適宜徳利 の傾き加減を察して熱燗してくれるから、オジサン二人は青春に戻ってテンションをあげていくことができる。 さて、一ヶ月前の”例会”の時、初めての話題が飛び出した。埴谷雄高「死霊」が講談社から文庫本三冊になって刊行されたという のである。しかも、増刷されているという。あの黒い装丁の箱に入った単行本がすぐ思い起こされた。(あの本はどこへいったんだろうか)。 先輩も同じことを思ったらしく、しばしそれぞれの記憶を辿りながら外側からトライした。しかし、アルコール漬けとなった記憶はそれ以上に 及ぶことができず、高橋和巳や吉本隆明へと移っていった。 数日後の会話。 「例の文庫本、A書店でⅠ巻を見つけました。B本屋ではⅡ巻。でもⅢ巻が見つからない」 「買ったの?」 「一冊が1,400円じゃぁ・・・」 と値段のせいにしたが、今改めて、あの四人兄弟が語りながら求めてゆく人間や生物、宇宙へと展開してゆく壮大な思考を読破す る自信は無い。おそらく、数ページも進まないのかも知れない。酒を飲みながらこんな話題に入ったのは数年来無かっただけに、ふと、 乱読ながらも充実していた過去が思い出された。たまには本も読まなければ・・・・。 詩誌「密造者」第58号掲載 横山仁 詩集「風」の前夜 〜詩誌「匪」からみる横山仁〜 |
| 横山仁が詩集「風」を刊行した。 はさまれていた紙片には、”なりゆきで30年ほどまえの作品をまとめることにしました(これで全部です)”とある。30年前と言えば横山 が26才頃で、詩誌「匪」(ひ)の同人になったあたりである。私もそのころ同誌の同人であった。「匪」に限って言えば、ここに収録され た作品14編のうち11編は同誌に発表されたもので、それ以外に横山の詩はない。評論はその前後を通じていききと発表され続け られたが、詩を外に対して示したのはこの限られたわずか2年間である。 その後、他誌等へ発表した詩作費品について聞く事は無かったから、横山が詩を外に対して示したのは、この「風」に収められた14 編が全てなのかもしれない。横山がわずか2年で燃えたのは何故だったのだろうか。 当時、論駁しお互いに自身の考えを伝えようともがいていた頃の記録の中に、何かしらの意味合いがあったのかもしれないと思い、 「匪」を読み返してみた。彼は言う。「匪」第27号、横山28才。”わたしは自分がなぜ詩をかくのかについての詩論を持たないではも う書けないのではないかという気がしている。(中略)もちろん詩は、書こうとしなければ書けないに決まっているが”と吐く。そして同誌 31号では、連作評論「ランボー(5)」の中で、吉本隆明の対談集の言葉を引用し自身を代弁させる。「一人前の詩人というふうに いわれているような、そういう詩人になるためには、1年か2年、毎日のように一所懸命ある程度の時間、詩を書くと、たいていの人が なれるんじゃないかと思っているんですよ。(中略)あんまり才能とか資質とかってのは、ないんじゃないかと思っているんですよ」。 横山はこうした”吉本の言葉をあてにして詩らしきものをかいていた”と述懐する。また、同誌34号の「ビンボーチョー(1)」では、”詩 が書けなくなって久しい。理由といえば、書こうとしないからとか、書くものがないからというよりも、もっと根本的なところにあって、要する に詩がなんであるかわからないらしい。自分のことを「らしい」と書くのは逃げているようだが、そうとしかいいようがないから、しかたない”と 自らの思考表現を振り返る。 ありきたりな言い方で申し訳ないが、その頃の横山が詩に出そうとしていたのは、生であり、自我であり、論理的な在りかたであった。 自身のための確認行為として詩を現すことで、併行して、自身の位置を探りあてようとしていたとも言える。 同誌の後半になって、詩がわからないというようなことを書いている箇所がある。詩を相当意識している証左だ。だからこそ、自身を 確認する行為の中で、詩という表現形態を、形固まる寸前にとどめたのかもしれない。それは、横山にとって詩は一つの表現形態、 ということに到達したからでもある。 石よ/やせた痛覚を殺がれ/土に融解する/静謐の重量にしなる石よ/死とは不意/ではなく慢性の病ではないのか (「円」) どんな存在の河も/夢の坑道を流れることはない/めくりとられたことばの表皮から/白い花のような老廃物がしたたり/うずくまるように かたまり/生の無意味さに篭もる (「水」) どこまでも倒れて来る影がわたしを/棒のようにつらぬいていることを識ったとき/ただ/わたしにむかって降りてゆけばよかったのである (「レクイエム」) わたしのなかで街が風化し/かれやきみも記憶の底に沈殿してゆくとき/わたしはわたしの意味をさがす (「街 (二)」) 30年ほど前、横山は私の詩集に対する評の中で、”たぶん前田はこの詩集に、みずからのアドレッセンスへの訣別の意味をこめた のである”と述べている。私はこのことばをそっくりそのまま横山に向け記しておこうと思う。 「秋田県現代詩人協会報第38号掲載 詩との出会い |
| 私が詩と出会ったのは中学校の頃であった。それまで自分の意思で本を読むことは勿論、ものを書くことなどしたこともなかった。親 兄弟にしても然り。それがちょっとしたきっかけで、以後現在に至るまでの約30年近く、詩とかかわることになったから不思議だ。 ものごとは偶発的な出会いで始まるとよく聞く。それが人によっては自身の中で深くかかわっていき、場合によっては人生観を変えて しまうほどの出来事にまで進展したりする。その出会いは人だったり物だったり趣味や自然だったりする。そうした諸々の事象を通じて人 は影響されてゆくのかもしれない。 大分昔のことだが、詩を書き始めて間もない頃、知人である絵描きの家によく出入りしていたこと があった。その知人から得た感性の重要さ、位置づけは今でも私の基本になっているが、出会いについて彼は「きっかけや出会いが偶 発性だとしても、感性が能動的でなければ関わりは生じない」と言っていた。自ら積極的にあれと口癖のように言い、感性を研ぎ澄ま せることが自分の潜在能力を表面化できる手立てだと強調していた。私と人との出会いである。 ふと、そんなことを思い出しながら自分と詩との出会いについて考えてみたら、そうした「感性の能動」的な部分ではなくて、中学校の 教科書に出ていた次の二つの詩、いわば与えられたものであった。 甍のうへ 三好達治 あはれ花びらながれ をみなごに花びらながれ をみなごしめやかに語らひあゆみ うららかの跫音空にながれ をりふしに瞳をあげて 翳りなきみ寺の春をすぎゆくなり み寺の甍みどりにうるほい 廂々に 風鐸のすがたしづかなれば ひとりなる わが身の影をあゆまする甍のうへ 鹿 村の四郎 鹿は 森のはずれの 夕日のなかにじっと立っていた 彼は知っていた 小さい額が狙われているのを けれども 彼に 彼にどうすることができたただろう 彼は すんなり立って 村の方を見ていた 生きる時間が黄金のように光る 彼の棲家である 大きい森の夜を背景にして 国語の教師はこの二つの詩を諳んじるように宿題を出し、毎回私達はつっかえながら朗読した。一通りできるようになってから、今度 は感想文を書く問題があった。どう感じ何を書いたかは忘れたが、このFという教師は間違いなく私に詩の世界をチラリと見せてくれた 人である。「感性の能動」的な出会いではなかったが、これがきっかけで新しい世界へと背伸びしたのかとも思う。 あらためて読み返してみる。 ・「甍のうへ」は憂いに満ちた、静かに移ろう<時>がなんとも切ない。流れてゆく時間の中で「ひとりなる/わが身の影>を<甍のうへ> にあ<ゆまする>実在感は、それまでの情景描写をもって効果的に位置づけられている。 ・「鹿」では、狙われているのを自覚しながら立っているしか術の無い生、凝縮された<時間>が見える。死と生のはざまで、今ここに生 きているというときの尊厳さを感じる。瞬時の中で静止する実在が痛い。 今にして思えば、こんなに時間をかけて読んだ詩は今までになかった。それではと思い拙作を探し出してみたら、潜在的に影響をうけ ていたのか<時間>にこだわっているのが見えてきた。 次は20代前半の拙作 風景 前田 勉 風景に閉じ込められた 自動車の空間 と その中の私 が 移動する密閉された意識の中で 移動するのは肉塊 発信寸前の時間に置いてきたのは・・・・・ あれは私ではなかったのか ハンドルを握りながら 私はふたつに割れた空間に二分する その両端の存在は 放たれた矢のように あるいは隕石のように 気ままに 落花する ガラス越しに流れる風景は その薄い隔たりがある限り 虚妄だ 私は出会いによる感性の目覚めを肯定する。それは、知人である絵描きが「感性が能動的でなければ関わりは生じない」と言った ことと相反するかも知れないが、受動的であろうとそのきっかけを自身の中で<出会い>として位置づけた時、つまりは感性が能動的 になっている時だからである。自身に対しても能動的でありたい。 「北のかたりべ」創刊号掲載 |