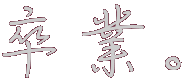
| 風はいよいよ強くなり、やがて、ふすまがガタガタと音を立てて揺れるようになってきた。遠くでは、かすかに雷鳴も響いている。 そして時折、風の音に混じって、なんとも形容しがたい、動物の鳴き声のようなものが聞こえてくるたび、ピチモたちは、ビクッと身体を震わせて、不安そうにお互い見つめ合うのだった。 「お・・・怒ってるんやでぇ〜」 朱莉、何か言わなくてはと、たまらず口を開く。 お喋りは、ビビリの裏返しなのである。 「うん、間違いあらへん」 そして、ひとり、自分のコトバに自分で納得する。 するとすかさず、となりから鋭い声が飛ぶ。 「違うよ。あれはただの野良猫」 愛美、こんな状況でも、相変わらずクールである。 「でも・・・。なんか人間の声みたいやん。不気味やわぁ。。。」 ぶるぶる体を震わつつ、今にも泣き出しそうな朱莉。 と、ここで。 「静かにしてっ!!」 狭い四畳半の部屋に、怒鳴り声が響く。 どちらかというと、ひそひそ小声でやりとりしていた朱莉と愛美。ハッとしたように、その声の主を見つめる。 「外の動きが聞こえないじゃん。黙っててよ!」 この場にいる3人のピチモの中でも、ひときわ身長が小さくて———というか、愛美と朱莉が大きすぎるのであるが———童顔の少女、友美は、顔を真っ赤にして怒っていた。 そして友美は、静かになった2人を確認すると、口元にべっとりとついた血をぬぐいつつ、再び耳をすませる。 ≪ズシン ズシン ズシン≫ やがて、地響きのような不気味な音が、どこからともなく伝わってくる。 ここで友美。待ってましたとばかり、パッと伏せ、畳に耳を押し付ける。 朱莉と愛美は、固唾を呑んで彼女の行動と表情をうかがう。 朱莉は、「まるで忍者みたいや!」と思ったが、口に出さずに飲み込んだ。 ややあって友美は顔を上げ、安心させるように2人の顔を交互に見る。 「大丈夫。まだそんな近くには、来てないみたい」 朱莉と愛美は、これを聞いて、同時に安堵のため息をもらした。 「なぁなぁ、ゆうみ。うちら、やっぱり間違ってたんちゃうか?」 しばらく沈黙が続く中、朱莉が遠慮がちに口を開く。 「はぁ!? 何言ってんの、あかり。うちらの、いったい何が間違ってたって言うの?」 友美の剣幕に気おされつつ、それでも朱莉は思い切って答える。 「せやかて、こんなことになってん———」 と、ここで、朱莉の瞳から、思いがけず、大粒の涙がこぼれ落ちた。 「うちらが、ムリに卒業しようなんて、しぃひんかったら、こんなこと・・・こんなことには」 対して友美は無表情のまま。 その目には、何の感情も浮かんでいない。 と、ここで。 「そんなことない!」 唐突に、愛美が割って入る。 「うち、これでよかったと思ってる」 「まな!?」 朱莉と友美は、普段クールで、あまり自分の意見や気持ちを出さないタイプである愛美の、その意外な自己主張に、やや驚いていた。 しかし、そんな2人の様子にかまわず、愛美は続ける。 「あのね。うちね。生まれて初めて、自分の意思で行動できたの。自分のやりたいことを自分で決めて、エイベックスのオーディションに応募して、合格して、ピチレ編集部に顔見せ行って。それでピチモになって。うん、すっごい開放感。それに、ねっ☆」 愛美は、部屋にあるカレンダーに目を移して。 そこには、日めくりのカレンダーがあり、数字は「28」とあった。 「それに、もうすぐ4月号の発売だもん」 この声に、友美と朱莉も、つられてカレンダーを見上げる。 そう。 今日は2月28日。柱時計は、夜の11時35分を指す。つまり、あと25分で3月1日———ピチレモン4月号の発売日となるのだ。 ここで、愛美の目が暗く光る。 「そうすれば、うちらの卒業号、卒業特集。もう、誰がなんと言おうと、高1ピチモは揃ってみんなで卒業できるんだもん」 そう言う愛美の表情は、いつのまにか自信と確信に満ち溢れていた。 「うん、そう。まなの言うとおり。うちらは、卒業できる。ううん、卒業しなくちゃいけない。だから、まな。もう喋らないで。まなは、もうずいぶん血を失ってるんだから」 やけに盛り上がる2人のやりとりを傍目で見つつ、朱莉は、愛美の首筋に開いた2つの穴と、そこから、うっすらと流れ出す血とを、複雑な気持ちで見つめるのだった。 ≪トントントン≫ ドアをノックする音。3人が、いっせいに顔を上げる。 「だ・・・誰や?」 「わからない」 「こんな時間に・・・」 続けて。 「♪ NaNaNa な な なめこ 晴れも雨の日も〜」 あまりにも場違いな、それはそれは可愛らしい歌声が聞こえてきた。 確実に家の外に、だれかいる。ドアの前に立って、歌っているのだった。そして、この声には、誰もが聞き覚えがあった。 「この声、もしかして、はるんちゃん!?」 真っ先に、友美が反応。 「うん。なめこちゃんやでぇ〜。この歌声、間違いないわ」 なめこグッズ大好きの朱莉も、興奮気味に。 しかし、愛美は冷静だった。 「ゆうみもあかりも、ちょっと落ち着いて! はるんは・・・、はるんは死んだのよ。聞いたでしょ、あなたたちだって。中2ピチモ林間学校で・・・無残にも首を・・・。どう考えても、即死だった」 落ち着いた口調で、2人を諭すように、愛美。 「しっかりしてよ、もう」 それでも、朱莉は、あきらめきれず、駄々っ子のように食い下がる。 「でも・・・。でも、あの声は、はるんちゃんや! あの、普段は口パク専用の、この前の『火曜曲』でさえも口パクだったはるんちゃんの、世にも珍しい生歌や〜!!」 すると——— 『ふすまを 開いて アラモ〜ド♪』 今度は、中に向かって呼びかけている。 「うん。まちがい、あらへん」 これを聞いて、朱莉が、思いもかけない行動に出る。 「あかりっ!」 朱莉は、パッとふすまに駆け寄ると、そのまま開け放ったのだ。 愛美は、そんな朱莉を無理やりにでも押さえつけようと手を伸ばしたが、一歩遅かった。 「はるん〜♪」 と、ほんの少しだけ、それこそわずか数センチ、ふすまが開いたその瞬間。 毛むくじゃらで、節のある、巨大で鋭利なカギ爪が、開いた隙間の上部から、躊躇無く朱莉に向かって振り下ろされたのだ。 次の瞬間、朱莉の首筋が、カギ爪に切り裂かれ、あたり一面に血が飛び散る。 さらに、爪は、再び振り上げられ、今度は、朱莉の細いウエストに巻きつくように絡みつくと、あっというまに、その体を部屋の外に引きずり出していった。 全ては一瞬の出来事だった。 あまりのことに、あっけにとられ、動きが止まる2人。 やがて、最初に気を取り戻した愛美が、ふすまに飛びつき、ピシャッと閉める。 「あかりが、あかりが、あかりが・・・」 友美が絶望的な声でつぶやく。 対して、愛美は、あくまで冷静である。 「あと15分。あと15分で3月になる」 これを聞いて友美。愛美に、鋭い視線を送る。 そんな視線を気にせず、愛美は続ける。 「そうすれば、ピチレを出て行ける———卒業できる!」 すると、ついにがまんでなくなって。 「でも、あかりは? はるんは? ほかのみんなは」 愛美に詰め寄る。 しかし愛美は、もはや友美の声など聞こえないかのように、さらに続ける。 「うちが奪われた時間、売り渡された時間は、4月号まで。そう、あと少し」 再び愛美の目に暗い光が宿った。 「見せ付けてやるんだから! うちらが卒業できるってことを、あいつらに突きつけてやる!!」 と、そのとき。 すうっと、なにやら生ぬるい風が、部屋を吹き抜けたような気がした。 2人は、反射的にビクッと背筋を伸ばした。 「ねぇ、まな。今の風、どこから?」 友美は不安そうに尋ねる。 「あそこ」 冷静に愛美は指さす。 「あの押入れからみたい」 そこは、部屋の隅っこにある、古い押入れ。 すると、何かに魅入られたように、ふらっと、友美が腰を浮かせる。 「ひょっとして、あの中に・・・」 まるで、吸い寄せられるように、ふらふらと押入れに向かう友美。 「やめて! ゆうみ、待って」 愛美が鋭い声で制するも、すでに、友美の手は、押入れの戸にかかっていた。 「待ってってば!!」 友美がパッと、戸を引くと——— ≪ゴォーッ≫ 一気に、ものすごい風が部屋に吹き込んでくると同時に、押入れの床が無くなっていて、そこは真っ黒の空間だった。 そして次の瞬間、なにか得体の知れないものが、ゆっくりと、じょじょに頭を覗かせてくる。 「ひっ・・・ひぃぃ」 友美は小さな悲鳴を漏らすと、急いでこの場を離れようとするが、そのまま足がもつれ、しりもちをついてしまう。 すると、押入れの底ら這い上がってきた物体は、ムカデのようにたくさんある足で、しっかりと友美の身体をとらる。 「うっ」 友美の喉から、奇妙な音が漏れ、たちまち顔が鬱血する。 「ゆうみ〜っ!」 しかし愛美は、動くことが出来なかった。 そのまま、ずるずると引きずられて、やがて押入れの底に消えていく、物体と、友美とを、ただただ見つめるだけだった。 二人が消えて、再び部屋に沈黙が訪れた。 残っているのは、たった1人の少女。 「あかり、ゆうみ。ごめん———ごめんなさい」 愛美は、畳に身を投げ出して泣き出した。 「うちが・・・、みんなを守れなかったばっかりに。うちは、ピチモのリーダーなのに。うちのせいだ。ぜんぶ、うちの・・・」 静寂の訪れた部屋で、愛美は1人、泣き続けるのだった。 ≪ボーン ボーン≫ 愛美の鳴き声以外、一切の音のしなかった部屋に、柱時計が不気味な音を立てる。 「ああっ・・・」 愛美は、これを期に泣き止む。 「ああ。ついに、4月号が発売されたんだ」 愛美は、天井を見つめて。 「おめでとう、高1スターピチモ。うちらは、ついに卒業したんだ。聞こえてる? あかり、ゆうみ。うちら、卒業したんだよ」 愛美は、笑みを浮かべつつ、ゆっくりと、ふすまに向かって歩き出す。 「うちら、ここを出て行くの。もう、どこにだっていけるんだ。『セブンティーン』へだって、『ポップティーン』へだって、『ノンノ』にだって」 そっと、ふすまに手をかける。 「ああ、なんて静かなんだろう」 ふすまは、音もなく開いた。 愛美は、外を眺め、目を細める。 3月の深夜。 凍えるような冷たい光が、暗い部屋の中に差し込んできた。 END |