
*****
-スペイン・マドリッド-
(一部抜粋)
どすん、という音と共に体に軽い衝撃を感じて、イベリア航空機はマドリッド、バラハス空港の滑走路をしばらく滑り、急に止まった。
ミキに会ったら、絶対泣こう。
荷物をかき集めて、まだシートベルト着用のサインが消えてないうちにいち早く、出口へ向かって行く。
冷房ですっかり体が冷えきっている。
ミキはべらべら喋りながら、酔っているんだか、ハイな状態なのか、踊るようにロビーを滑っていった。
泣くチャンスは、はずされた。
「スペインはえらい暑いからね。」
ミキは荷物を奪って引きずりながら、バスに乗り込もうとしていた。
一瞬何が起きたんだかわからなかった。
それくらい、冷えた体には異次元の暑さだった。

*****
「今、考えんとあかんのは男より金やわ。」
目からウロコだ。
こんな真実はなかった。
日本人は世界一金持ちだと言われようが、アフリカで大勢の人が飢えていようが、
現実はスペインの安宿に女ふたり、一日4285円なのだ。
一週間の命ではあったが、生きる目的を与えられたように高揚した気分がしゃきっとさせたが、一瞬に崩れ去った。
ここではミキなしには何もできない。
やっぱり気弱になっていた。
「とにかくせっかくマドリに来たんやから、遊びにいこうよ。」
ミキに連れられるまま、近くのバールで何かを食べ、どこかまでタクシーに乗って、着いた場所はアルチーというディスコだった。
なんでもプリンスがコンサートの後来たところだそうで、一階はしゃれたレストラン、
地下が白を基調としたコンテンポラリーな内装のディスコだが、そんなことはどうでもよかった。
まったく気分ではなかった。
しかし、音楽はいい。
今まで聞いたことのない気だるく、妖しげな曲。
どこかアフリカを思わせる旋律にヨーロッパの洗練さを加えた地中海の音楽だった。
元気があったら、真っ先に踊るのに残念だと思った。
ワンドリンク付きの入場料をやっと払ったのだから、これ以上飲んで無理矢理盛り上がることもできなかった。
ミキはもうかってに踊っていた。
仕方なくひとりで、ひんやりしたコンテンポラリーな椅子に座った。
ここもやけに冷房がききすぎている。
まったくもって、身も心も冷えきっていた。
キャメルの広告塔の温度計は39度を指していた。
翌日ミキとふたりでスペイン広場のベンチに座っていた。
起きたのは午前の11時で、たっぷり睡眠をとったはずなのにまだぼうっとしている。
風はなく、湿気もなかった。
からっと、さわやかなアメリカ西海岸の気候とも違っていた。
あくまでもストレートで、それでいて呑気な暑さだ。
隣のベンチには男の子がひとりで、何がそんなにおかしいんだか本を読みながら声を出さずに大笑いしていた。
無声映画を見ているようだった。
きっと暑さで聴覚がやられたのに違いない。
やるせなかった。
自分のじとっとした気持ちとの違和感に呆然としていた。
本当は北陸あたりで日本海に佇むべきだったかもしれない。

*****
パラスのロビーの椅子に腰掛けたとき、少し元気が出てきたような気がした。
パラスは13世紀に建てられたベル・エポック最後のホテルでその凛としたシルエットと内装の優雅で荘厳な雰囲気はパリのようだった。
土屋さんにご馳走になってお腹が満たされたのか、
あの後散歩した小さな公園で見掛けた男の子のサファイアのような瞳がなんともいえず美しかったからか、
シエスタの最中だというのに入れてくれた場末のバールで、
店の人がテレビのサッカー中継に夢中になっている中飲んだビールのおいしさのせいか、よくわからなかった。
ミキはやっとスペインに慣れたんやろ、と言ってこっちが段々ミキのペースになってきたことを喜んでいる。
バカルディ コン リモーネをすすりながら、一階のフロアーに出てみると軽いノリの曲がかかっているのにもかかわらず、
誰も踊っていなかった。
皆グラスを片手に喋ったり、体を揺すったり、女たちは扇子で冷房の風を扇いだりしていてフロアーには背を向けていた。
化粧室のすぐ近くに立った。
まず女たちは入り口に入ってくるなり、回りの人々をぐるっと一瞥しただけで化粧室に直行する。
もう十分すぎるほどの化粧の上にさらに仕上げのマスカラを念入りにその長い睫に上下から塗り付ける。
そして舞台へとご登場だ。
体にぴたりと張りついた布はこぼれ落ちそうな胸とはち切れんばかりの腰をなんとか隠していた。
六本木のボディコン娘の比ではない。
肉体をあますところなく意識させてしまう、本物のボディコンシャスだ。
男たちは筋肉質の体に柄物のシャツを羽織り、はだけた胸からゴールドのチェーンと胸毛をちらつかせる。
艶やかな黒髪をオールバックになで付けて、そのマッチョぶりを誇示していた。
そしておもむろに女たちの体に目をはわせ、物色した後、獲物に向かって巧みに近づいていく。
もちろん女は自分の発したフェロモンを察知してくれた幸運な男を受け入れる。
その動物的な求愛の遊戯は圧巻でさえあった。
一部始終を見ていた自分の方がよっぽどいやらしいと感じてフロアーの方へ目をそむけた。
皆何かが始まるのを待っているのだった。
快楽の頂点へ行くのに前戯があるように、じわじわと上り詰めるまでをじらしていた。
スペイン人は快楽の持って行き方を本能的に楽しんでいる。
ミキと顔を見合わせて、年上の余裕の笑みを交わしてからフロアーに近づいていく。
露骨なアプローチには素早いアクションで応えないといけない。
最初の誘いにはいったん断るのが日本風の礼儀のように、どの国にもあうんの呼吸の作法がある。
「この曲、誰が歌っているんだっけ?」
ミキはさらに熟練した技を使って、男の子のひとりに話しかけた。
その答えは解明されなかったが、ミキが話しかけた男の子はミゲール、もうひとりはモロッコ人のムスタファだということがわかった。
ふたりが飲み物を調達に行っている間、ミキはやったね、また二杯めタダになったやん、と自分の手腕に惚れ惚れするように言った。
こういう女たちばかりが海外旅行をしているとすれば、確かに日本人の女は相当なワルだという噂がたっても仕方ないだろう。
ミキとミゲール、こっちはムスタファと自然に分かれてそれぞれ椅子にすわった。
ムスタファは1年前からエンジニアの学校に通うためマドリッドに来ていて、
スペイン語とフランス語とアラブ語しかできないということだけミキが通訳してくれた。
両手を使って家族は何人いるかという非常にプリミティブな会話をした。
グラスが空になりかけて、男の子たちの手が段々腰に下がってきたのを頃合いにミキがもう帰らなきゃ、
と急に塩らしく宣言してオスタルに戻ってきたのだ。
5人兄弟の3番めだというムスタファの目は素直で、純朴な中にも血気盛んな情熱を秘めていた。
やっぱり口直しが必要だ。
トム・ウェイツのしゃがれたブルースが場末のバールの壁に染み込んでいく。
煙草を吸うとさっきから飲んでいるアルコールの酔いが一気にまわってきた。
歪んだ顔の女にスキンヘッドの教授、ブルース、ミキの隣の席ではこの店のマスターらしき男がゆっくりとマリワナを薄い紙に巻いていた。
あまりにもできすぎていると思った瞬間、目の前に知らない男の子が立っていた。
「ぼくの日本人のガールフレンドはユキコっていう名前だったよ。」
誰も聞いていないのに甲高い声で天井に向けて喋っている。
柔らかな髪を真ん中分けに垂らし、びっくりするほど端整な顔をしていたが、そのきれいなブルーグレイの瞳は完全にトンでいた。
小柄な体に白いシャツと黒いベストを引っ掛けている様はちゃんとしていたら貴公子といったかんじだ。
それにしても扉が開いた気配はしなかったし、一体この子はどこから降ってきたのだろう。
このラリった貴公子の登場と共にトム・ウェイツから南米のサルサ風の曲に変わった。
「ランバダを踊ろうよ。」
ミキの手をとって腰を振りながら隅の方へ寄っていった。
本当にランバダがかかり、ラリった貴公子はミキの体を引き寄せると巧みな動きで見事に踊った。
かなり際どい動きのダンスだが、貴公子には不思議といやらしさはない。
時々体を二つ折りにされてのけぞったミキはケタケタと笑っている。
今度はスローなボサノバ風に変わり、貴公子に触発されたのかスキンヘッドの教授がゆっくりと手を取ってフロアーに促した。
ミキと貴公子はまだランバダの振りのままだ。
何の曲かは忘れたが、絶対どこかで聞き覚えのあるフレーズだ。
スキンヘッドの教授は肩から腰に手を回し、抱きしめてきた。
目を閉じてかすかに首を振っている。
昔の恋人の亡霊をさながら抱きしめているようだ。
もうここまできたらどこまでもオフビートな集まりの夜だ。
ふと、この場面はいつか見たことがあると思った。
デジャヴが襲ってくる時のめまいで足がよろけた。
その振動で一瞬夢から覚めた教授が薄目を開けてほほ笑んで、さらにきつく抱きしめて、また幻想の世界へ戻っていった。
ダウン・バイ・ローだ。
ジム・ジャームッシュの作品の中でも一番好きな映画だ。
徒労の末にたどり着いた家でロベルト・ベニーニが恋した女主人と明け方踊るのを、しらけた顔で眺めるジョン・ルーリーとトム・ウェイツ。
アングル的にもあの場面にそっくりだった。
バールを出ると夢見心地のスキンヘッド教授組みは左へ、浮かれてラリった貴公子組みは右へと分かれた。
ダウン・バイ・ローの最後の場面でも残されたふたりは別々の方向に分かれる。
その先に何があるのか、お互いにまた会えるのか、そんなことはちっともわからない。
だから小気味いい。
夜明け前で涼しくなった通りを急に無口になった教授と手をつないで歩いた。
エチェガライだというと教授はおとなしく角まで送ってくれた。
オスタルの前にはミキがひとり無事に立っていて、ほな、寝よか、とあくびをした。

牛の動きがスローモーションになり、いきなり夕日の中でどっと倒れた。
観客がいっせいに白いハンカチを振り、立ち上がった。
心臓に命中した見事な演技だったのだ。
闘牛は牛の野生に勝る人間の知恵と勇気を技と芸術で見せる儀式だ。
スペイン人のようにそのアートとセレモニーを称えて楽しむ気持ちにもならなかったし、
アメリカ人のように殺されていく動物がかわいそうだとも思えなかった。
いったんアレナに立ったら、どちらかが傷つかなくてはならない。
それはもう宿命なのだ。
境界線がソレ側を包みこんで太陽の位置が低くなっていた。
興奮した人いきれのなかで初めてスペインに来てよかったと思った。
2曲、3曲と踊っているうちに体が勝手に動いて止まらなくなった。
おもしろがって入れ替わり立ち替わり目の前に人が現れては消えていく。
クリーム色のスーツを着たモデルの男の胸から垂れたハンカチが、
なまめかしく浮かんでいる。
ブルーの照明の中で人々が海底の海草のように揺らめいていた。
過去もない、未来もない、感傷もない陶酔感が体中にひたひたと回ってきた。
修行僧が悟りに至るときはどんなメディテーションを体験するのだろう。
覚醒にも似た幸福感がきっとあるはずだ。
突然白いものが天井からひらひらと舞ってきた。
イベントの演出で雑誌の広告のコピーが2階からばらまかれたのだ。
照明が変わってその白い紙だけが蛍光作用で青白く光っている。
よかったんだ、これで。
この瞬間が体験できた。
現在が今ここに存在している。
ミキがコロン広場までバスで送ってくれた。
いろいろありがとう、と言う間もなくじゃあね、と言って普通に別れた。
いっしょに旅行するならミキはどんな男よりも頼もしい存在だ。
今度会うのはいつになるのだろう。
フラメンコのドレスを着たダンサーがオレ!とポーズをとった姿が古びた印刷で、
スカートのところだけが立体的に布地が貼り付けられているポストカードを取り出した。
何をしているのだろう。
突然、この葉書はもう出す必要がないと思った。
ここで日本語が読める人はいないだろうが、よっつに破ってゴミ箱に捨てた。
フラメンコのスカートの黄色がゴミ箱の中でひらひらと旗めいていた。
急に荷物をひとつ降ろしたように肩が軽くなった。
黄色を選んだのはどうしてだったろうか。
黄色のバラは嫉妬という花言葉があるし、どこかの国では勝利の象徴でもある。
すっきりとした気分になって、税関のおじさんの挨拶にムイ・ビエンとウインクして答えた。
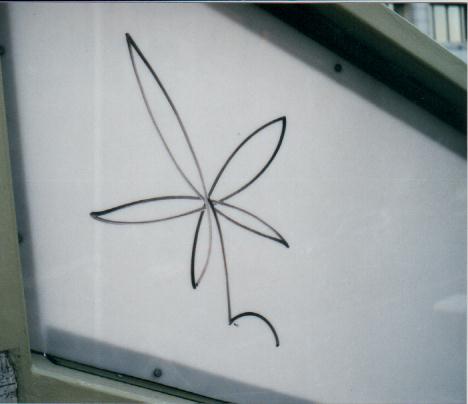
*****
ムーチャス・グラシアス、おばさんは微笑んでそう言うと、皺がさらに細かくなった。
機体がゆっくりと滑ってエンジン音が強くなったかと思うと離陸した。
斜めになった機体から赤茶けた土とところどころに緑のあるスペインの大地が見え隠れした。
ムーチャス・グラシアス、そう、スペインに救われた。
人間とことん落ちると反動で急上昇するのかもしれない。
荒療治だったかも知れないが、マドリッドの夜が確実に救ってくれたのだ。
笑おうとして顔の筋肉を横に伸ばしたら、真っ青な空が揺れて見えた。
隣のおばさんが肘をつついてシートの倒しかたを聞いてきた時、右目から涙がつぅっと流れた。
おばさんは怪訝そうにどうしたのか、というようなことを言って顔を覗き込んだ後、バックからハンカチを取り出して頬にあててくれた。
何でもないんです、ごめんなさい、と英語で答えたが、おばさんは尚も何か喋って手の甲をさすってくれる。
それは泣きたいときには泣いていいんだよ、と言っているように聞こえた。
それでおばさんの皺くちゃのハンカチを奪って、その中へ顔を埋めた。