
「神様の木」 No.2
−27−
2人は心のスケッチブックにそれぞれの空を描いた。
ネロは、新しい空に旅立っていく白い鳥をバックに明るい色彩の青空の上に描いた。
一方、カイトの空は、自分と違う世界に旅立って行く鳥を見送るどこか淋しい夕焼け空だった。
「シチューが出来たよ」
ネロが最後の味見を終えて、カイトの方を振り向いた。
もう空はほとんど陽が沈みかかっていた。
晩ご飯は2人肩をよせ合って食べた。
真夏とはいえ、ドーンの森の夜風は薄着の2人には肌寒かった。
ネロの作った暖かいシチューはカイトの心にじんわり染みた。
「おいしいよ」
「うん」
ネロはカイトにおかわりをよそってあげた。
2人は仲良く切り株の上に座って星を眺め
−28−
ていた。
ドーンの森で2人っきりで見上げる夜空は、いつもの星空よりも数倍迫力があって、輝きも倍増して見えた。
「星空が綺麗だね」
「うん」
ネロはいつになく無口だった。
カイトは包帯の巻かれた親指を所在なげにぶらぶらと動かしていた。
そんなに大したことはなかったようだ。
食器を片づけて、リュックの中にしまった。
テントの中に銀のマットを敷いて、2人は並んで横になった。
懐中電灯のスイッチを消すと、ドーンの森は全くの暗闇に包まれた。
「ほんとうに真っ暗だね」
ネロとカイトは感心したように、黙ってテントのなかでしばらく横になっていた。
あまりの沈黙に耐えられずに、カイトが手に持った懐中電灯をぱちんぱちんと灯けたり
−29−
消したりした。
懐中電灯の明かりが灯るたびに、ネロは眩しそうに目の前に手を翳した。
「電気ってほんとうに明るいんだね」
無邪気に笑うネロを見て、カイトはなにかを心に決めたようだった。
「これから昼間に見たあの神様の木のところまで肝試しに行こうよ」
ネロは初めびっくりとして、どこかきょとんとしたようにカイトを見つめていたが、カイトの真面目な目に気づくと、
「うん」
と黙って頷いた。
ネロとカイトは懐中電灯の光だけを頼りにテントから出てドーンの森の小道を歩き出した。
2人の影は長く長く伸びて、カイトの大きな影とネロの小さな影がよりそって歩いていた。
−30−
「こっちの道だったような気がする」
ネロがそう言って、分かれ道で右の方を指さした。
「甘い樹液の匂いがするよ」
確かにネロが指した右の方向からは、どこか髪の甘い匂いにも似た懐かしい感情を呼び起こさせる香りが漂ってきていた。
「虫がこの香りに引き寄せられる気持ちも分かるな」
「カイトは虫なの?」
ネロが懐中電灯でカイトの顔を真下から照らした。
「飛んで火にいる夏の虫ってことわざ知ってる?」
「ううん」
カイトは首を横に振った。
「火に飛び込んじゃうくらい、周りのことが見えていないっていう状況の中にいる人のこと、危険だって分かっているのに、飛び込んじゃうんだ。後先かえりみずにね」
−31−
「それで?」
「もちろんその虫は死んじゃうんだよ。なんていったって火だもの。羽根ごと焼かれて死んじゃうんだよ」
「今の僕はそういう風に見えるのかな」
「多少ね」
ネロはコホンとひとつ咳払いをした。
暗い森の静けさの中で、音は昼間よりも数倍大きく響いた。
2人はずっと黙って、昼間来た小道を歩いていた。
昼間見たときとは景色も全然違って見えて、全く別の道を歩いているようだった。
「懐中電灯の光くらいだったらきっと大丈夫だよ」
そう言ってネロは懐中電灯を丸く、くるくると小さく振り回した。
「よく夜中、街灯に群がっていて朝になると死んでいる虫っているじゃない。ああいう風にはならないでね」
カイトはなにかよく分からないというよう
−32−
に首を振った。
「今の話は抽象的すぎてよく分からない」
カイトの正直すぎる答えに、ネロはふふっと笑った。
「指のケガは大丈夫?」
「うん、少し痛むだけ」
カイトは親指をネロの前でゆっくりと動かして見せた。
「さっきの意味は?」
「分からなかったらもういい」
そう言って懐中電灯を足下に向けた。
「命は大切にしてね、カイト。一度しかない人生なんだから。きみの生き方を見ていると時々、心配でならないんだ。気をつけてね。ほら、よく見て。段差があるんだから」
木の根が大きく飛び出たところにつまづかないようにカイトは足を大きく上に上げた。
「きみが好きだから、心配なんだよ」
カイトはじっとネロの顔を見つめた。
ネロは素知らぬ顔で、話を続けた。
−33−
「心配じゃなかったら、好きじゃなかったら忠告なんてしないし、きみと一緒にキャンプなんか来ないし、こんな真夜中に肝試しなんかしない!」
ネロはどこか晴れ晴れとした顔つきで、カイトの目の中をじっとのぞき込んだ。
夜光虫がくるんと光の帯を丸くなぞりながら、遠くへ飛んでいった。
「ありがとうな」
カイトがそっとネロの手を握った。
今度はネロがそっとカイトの手を握り返した。
「今から引き返す?」
「ううん」
カイトがはっきりとした口調で答えた。
「大丈夫だから、僕についてきて」
カイトが数歩先に立って歩き出した。
樹木の甘い匂いはだんだんと強くなってむせ返るようだ。
蛾に似た白い文様の蝶々が夜の闇の中を
−34−
数十羽乱舞していた。そっと触れたネロの指に白い花粉のような粉の感触が残った。
その時───。
ホーホーというふくろうの鳴く声が突如、ドーンの森の中に響きわたった。
「あの伝説の白ふくろうだよ」
カイトが声を上げた。
「そうだったらいいね。あまり大声を出したらせっかくのふくろうが逃げちゃうよ」
ネロが人さし指を口に当てて、しーっと合図した。
またふくろうの鳴く声が今度は3回した。
「近いよ。きっとこの近くにいる」
2人は忍び足で、ふくろうの声のする方に歩き出した。
先ほどの不思議な白い蝶々がネロの額に当たって下に落ちた。
「踏まないでね、カイト」
ネロが小声で囁いた。
−35−
「みんな生きているんだから。森の中の動物はみんな同じ命を持って生かされているんだよ」
カイトが黙って頷いた。
気づけば、白い蝶も黒と灰色の斑点のある蛾の群も薄茶色の羽虫もその他たくさんの虫が一方向に流れるように飛んでいた。
足元をすりぬけていく物があると、下を見ると黒いうさぎと白いうさぎが先を急ぐようにカイトの横を駆け抜けていった。
木の上の小リスもそれに続けとばかりに、木と木の間を上手に飛び移って去っていった。
「何が起こるんだろうね」
少し不安そうなネロに、
「心配しないで、僕がずっとそばについているから」
とカイトが答えた。
甘い樹液の匂いが夜風に絡んでむせかえりそうだ。ドーンの森の動物に導かれるままに
−36−
歩んでいくと、気づけば昼間2人で来た「神様の木」の前に立っていた。
白くぼーっと光る物体が、枝分かれした3番目の幹の上に在った。
よくよく目を凝らすと、それは伝説の白ふくろうだった。
ネロとカイトが見上げると、白ふくろうはクークークーと3度、静かに鳴いた。
神の木の周りには無数の動物達がいた。
様々な種類の野ウサギに、シマリス、イタチにテン。大小のの野ネズミに野生のキツネ。遠くにはクマの親子の姿もあった。
色とりどりの花が咲き乱れ、暗闇の中に発光するようにぽーっと幻想的に浮かんでいた。
白、茶色、灰色、黒、深紅、深紫色の様々の種類の蛾に似た蝶が宙を舞っていた。
ドーンの森中のすべての動物が見守る中、白ふくろうはかっと目を見開いた。
その黄色の眼光は、森中を皎々と照らし出した。
−37−
「これから、このドーンの森の神様が姿を現す。儀式はこのわたしホワイトアウルが取り仕切るので皆はそれに従うように」
威厳に満ちあふれた白ふくろうの言葉に、動物達は一斉に尻尾を縦に振った。
「それではドーンの森の賛美歌301番を斉唱」
白ふくろうが、左の羽の下から小さな木の指揮棒を取り出して小さく振った。
どーんという太鼓のような音が神の木の根本付近から響いて、続いてカエルのケロケロケロという合唱が始まった。
それに羽虫のぶーんという音が混じって、収拾がつかなくなったのではと思われた瞬間に小鳥達の心洗われるコーラスが始まった。
今までに1度も聞いたことのない奇妙な旋律を奏でるそのドーンの森の賛美歌301番のメロディーは、不思議なことにカイトの心の琴線を鷲掴みにして、どこか遠くの異国の辺境まで連れていかれるような気持ちにさせた。気づけばカイトは涙をぽろぽろと流していた。
−38−
「心洗われる歌だね」
隣でネロが黙って頷いた。
天国ではずっと美しい旋律が流れていると聞いたことがある。その音楽とはこういう感じなのだろうか、とネロは思った。
音楽がぴたりと止むと、神の木の根本に近い部分から古い扉らしき物が現れて、ぎーっと軋んだ音と共に扉が開いて、神様が姿を現した。
神様は白銀のように静かな光を放つ長い髪と腰辺りまで達する長い髭を蓄え、月の光を封じ込めたような金色の閃光を投げかける長い長い杖を持っていた。
白ふくろうが両翼をぱさぱさと羽ばたかせて神様に丁重な挨拶をした。
他の動物達もそれに習って、足を振り上げたり尻尾を水に振り当てたりして、尊敬の念を各自それぞれに表現していた。
「うわぁー」
ネロが感激のあまり、感嘆の声を上げた。
−39−
そして、カイトについてきて良かったと、そっと耳打ちをした。
カイトは誇らしげだった。
一匹の雌鹿がネロに歩み寄ってきて、耳元にこそりと囁いた。
ネロは真剣に耳をそばだてて、時折ふんふんと頷いていた。
「なんだって?」
雌鹿が群の中に帰っていくのを見届けてからカイトがネロに尋ねた。
「このドーンの森の守り神の前では口を慎むようにだって」
ネロは小声でカイトに囁いた。
「すごいね、ネロ。動物と会話してるよ」
ネロは微笑んだまま口を閉ざした。
これから起こる、すべての現象を一つ残らず見逃すまいとでもいうように。
森の神様の前で宴会が始まった。
まず最初に、小リスがぐるっと手と手をつないで、輪になって円舞を始めた。
|
|
−40−
踊りが終わると、一匹一匹の小リス達に、神様からクルミが手渡された。
周りから自然と拍手が起こった。
カイトとネロも一緒に手を叩いた。
その時───。
カイトは神様の右手に白い包帯が巻かれているのを見逃さなかった。
カイトはそっと、右のポケットのジャックナイフに手をやった。ナイフの刃には、昼間神の木を傷つけた時の生々しい樹液の匂いがタトゥーのように残っていた。
気づけば、カイトはネロの制止を振り切って宴たけなわの踊りの中に飛び込んでいた。
神様はびくりともせずに、目の前のカイトを静かに見つめていた。
「神様ごめんなさい。僕は今日、このナイフで木を傷つけました」
カイトは神様の前で、ぽろぽろと涙を流した。神様の右手の包帯には、じんわりと血が滲んでいた。
−41−
カイトは神様の手をとって、その傷の上に接吻をした。
ネロは隣で黙って見つめていた。
神様はようやく重い口を開いた。
「木々をむやみに傷つけてはならない。小さな命をいたずらに殺してはならない。この森で生きていくための掟だ」
カイトは涙を流しながら、黙って頷いた。
「すべての生きとし生けるものには命が宿っているその光が見えるか」
神様の穏やかだが妖しい光を宿した強い眼差しは、静かにカイトの潤んだ瞳を見つめていた。
振り返ったカイトの前には不思議な光景が広がっていた。
周りをぐるっと見渡すと、ドーンの森のすべての木々に明るい光が灯っていた。
すべての植物の上には光の霧が懸かったように夜霧を含んで、きらきらとそれぞれの命の光が自らを誇るように煌めいていた。
−42−
よくよく見ると、すべての動物の上にも、そしてカイトとネロの頭の上にも、天使の輪のような白い光が明々と灯っていた。
その光景は壮観だった。
「命の光なんだ」
「綺麗だね」
ネロとカイトはお互いに見つめ合った。
光にも色んな種類の光があった。生まれたばかりのヒナの光は黄色くてぼんやりしている。雌鹿の角からは散乱するように赤い光が放たれていた。年老いたクマからは、灰色がかった褐色に近いどんよりした、どこか落ち着いた色の光が周りに満ちていた。
植物の光りは全体に、穏やかで優しかった。
心にすっと水が体になじんで潤っていくような優しい感触の光り───。
神様の木からは、荘厳な感じを与える清らかな聖なる虹色の光りが枝という枝から放たれていた。
−43−
森の神様は、ネロとカイトを呼び寄せた。
持っていた金の杖をひと振りすると、カイトの親指の包帯がするりと解けて、傷が跡形もなく治っていた。
カイトの全身からは淡い銀のヴェールのような光りが放たれていた。
「ありがとうございます」
神様は大きく頷くと、
「今夜見たことは、むやみに人に言わないように」
カイトは黙って頷いた。
「昼間のことはごめんなさい。許していただけますか」
カイトは樹液の付着したジャックナイフを神様に差し出した。
神様は黙ってナイフを受け取ると、森の住民たちを引き連れて夜の森を歩き出した。
神様が着いた先は湖水のほとりで、水は紫水晶の煌めきを宿していた。
神様はカイトのジャックナイフを、湖の底
−44−
深くに沈めた。
最後にドーンの森の神様は、カイトに青い石に銀の鎖のペンダントを、ネロには赤い石に金の鎖のペンダントを授けた。
神様はカイトには疫病災害から避けられるおまじないを、ネロには英知が宿るおまじないをそれぞれのペンダントに祈りを封じ込めて下さった。
「ありがとうございます」
カイトとネロは神様に深々と頭を下げた。
「カイトもネロも元気でな。すべての命の枝は木の幹のように一つに繋がっていることを忘れないように」
神様はそう言い残して、扉を閉めた。
数秒後には扉は跡形もなく消えていた。
周りを見渡すと、すべての動物がそれぞれの住処へと引き揚げていくところだった。
白い霧のような光りだけがあちこちに残っていた。
−45−
次の朝、気がつくとカイトとネロはテントの中で眠っていた。
「昨日起きたことは本当だったのだろうか」
カイトがテントの中で起きあがって、全身をくまなく眺めていた。
親指の傷は見事に跡形ひとつなく治っていた。
空は夏の朝らしく、高く澄んでいて気温が高くなる前のまだひんやりとした森の空気が辺りに満ちていた。
鳥のさえずりが遠くの方で聞こえて、小川のせせらぎが喉の渇きを促した。
「朝食にしようか」
ネロが赤いリュックサックから、食パンとレーズンパンと牛乳とハムを取りだした。
「昨日はすごい体験をしたな」
「ヤン先生の言っていたとおりだったね」
カイトとネロはパンを頬張りながら、なつかしそうに昨日の話の続きをした。
「夢のようだったね」
−46−
「まだ夢の続きを見ているみたいだ」
ネロはしばらくじっと小川のせせらぎに耳を澄まして考え事をした後、赤いトレーナーの下から金の鎖の付いた赤い石のペンダントを取りだした。
「神様からもらったペンダント、カイトも持っているよね」
カイトが慌てて、体中をぱたぱた押さえてペンダントを探した。
左のポケットに治ったばかりの手を伸ばすと、なにか触れる物があった。
取り出すと、昨日神様がカイトにくれた銀の鎖の付いた青い石のペンダントだった。
「よかった」
カイトは本当にほっとしたように、早速青いペンダントを首に掛けた。
「カイトは本当に体に気をつけてね。もちろん事故にも。いつもそそっかしいんだから」
ネロが青いペンダントを見つめながら、カイトにそう言った。
−47−
「そして、僕は新しい学校に行った後も。勉学に励まないとね」
「無理をするなよ」
カイトが優しく声をかけた。
「うん」
ネロが朝日の中、微笑んだ。
「違う学校に行っても、絶対に会おうね」
カイトがネロの手をしっかりと握った。
「この森で見聞きしたことは、クラスのみんなには内緒だぞ。2人だけの秘密だ」
ネロは黙って頷いた。
2人は、明るくなっていく空を一緒に見上げていた。
夏休みが終わって、始業式の日。ネロとカイトはヤン先生を訪ねに教員室の戸を叩いた。
ヤン先生は、長椅子に腰掛けてうたた寝をしていた。
「ヤン先生」
ネロとカイトが後ろからそっと声を掛けた。
−48−
ヤン先生はびくっと驚いたように目を開けて、まじまじと2人を見た。
「ああ、君たちか。夏休みの間はどうだったかな。2人ともすっかり日焼けをして、夏前よりも健康的になった」
「ありがとうございます」
ネロとカイトはヤン先生に頭を下げた。
「先生の勧めてくれたように、2人でドーンの森でキャンプをしたんです」
ネロがヤン先生に話し始めた。
「テント張りも、炊飯も全部2人だけでやってのけたんです」
カイトが誇らしげに胸を張った。
「ところで、不思議な現象は起こらなかったか?」
ヤン先生がネロとカイトの顔を交互に見ながら、話を進めた。
ネロとカイトは、ちょっと顔を見合わせた後、
−49−
「はい、大変貴重な体験をドーンの森でさせてもらいました」
と元気に言って笑った。
「森の声は聞こえたかい」
「はい」
ネロとカイトは嬉しそうだった。
「白いふくろうの伝説どおり、命の光りは見えたかい」
「はい」
ネロとカイトの瞳はますます輝いた。
「森の神様は何と言っていた?」
ヤン先生が目をつむって尋ねた。
「木々をむやみに傷つけてはならない。小さな命をいたずらに殺してはならない。この森で生きていくための掟だと、すべての生きとし生けるものには命が宿っている。命の枝は木の幹のように一つに繋がっていることを忘れないように、と」
ヤン先生は少年時代の遠い昔をなつかしむように、じっと目を閉じて2人の教え子の話
−50−
に聞き入っていた。
「なつかしい……私はあの時の、ドーンの森の風の匂い、光りもすべて覚えている。ついこの間、起きたことのように」
ヤン先生はゆっくりと目を開けて、机の前に置かれたセピア色の写真を眺めた。
そこには神様の木の前で微笑む少年時代のヤン先生の姿があった。
来年の春に、長年勤め上げたこの学校を去るとヤン先生は言った。
去年の3月でもうヤン先生は70才を迎えられる。髪の毛も夏の間、見ないうちにすっかり後ろの方まで白くなった。
「さびしくなりますね」
ネロは、切なそうに言った。
「新しい学校に行ってもしっかり勉強をして」
ヤン先生はそこで言葉を切って、ネロとカイトをしっかりと見つめた。
「ドーンの森での出来事を、大人になってもしっかりと心にとめておくように」
−51−
ヤン先生の言葉は2人の胸にじんわり沁みた。
「先生もお体に気をつけて、長生きをしてください」
ヤン先生は黙って微笑んで、机の1番上の滅多に開けられたことのない引き出しを開けた。そこには緑の石のペンダントが、長い時を越えて燦然と輝いていた。
ヤン先生は緑の石のペンダントを首に掛けた。
「神様から授かった石ですよね」
ヤン先生は、
「そうだよ」
と優しく答えた。
ネロがヤン先生にそっと尋ねた。
「ヤン先生は、子供の頃、神様になんと言われたんですか」
「当時から、学校の先生になりたかった私はドーンの森の神様に、命の大切さを生徒に教
−52−
える先生となってしっかりと勤め上げるように言われたのだ」
ヤン先生は、窓の外の遠くに見えるドーンの森を眺めながら、感極まったように泣いた。
ヤン先生の胸に掛けたれた緑の石は、太陽の光を受けて誇らしげに輝いていた。
終わり
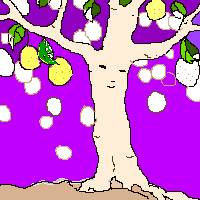
鈴蘭さん作