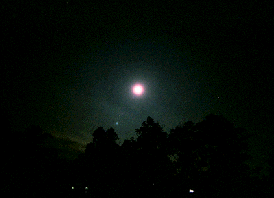Your Voice
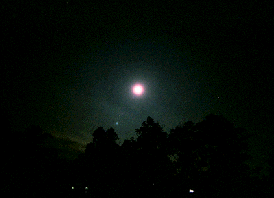
「おやすみ…」
別れを告げる言葉を無理に押し出し、相手が受話器を置くのを確認すると、アリスは握り締めていた受話器を戻しながら溜息をついた。
電話の相手は、アリスと同じ英都大学の二回生・火村英生。今から4ヶ月ほど前、法学部の講義を聴講しに来ていた社会学部の彼に書きかけの小説を読まれて以来、行動を共にしている。
電話をかけたのはアリス—
『もしもし、火村?俺や』
『なんだ、アリスか』
すぐに自分だとわかってくれることに安堵する。
『あんな、俺のペンがないんや』
『は?』
火村は「わけがわからない」というような声を出した。そんな彼の姿が安易に想像できて、アリスは思わず口元を緩める。が、それを悟られないように、ちょっと困っているような声を出す。
『大事な黒いペンなんやけど、見当たらないんや』
『…で?』
『今日も使うてたから、もしかしたらおまえのペンケースに入っとらんかな思うて』
今日も火村は法学部の講義を熱心に聞いていた。そしてアリスはというと、そんな火村の隣の席で次の賞に応募するための小説を熱心に執筆していた。
『…ちょっと待っとけ』
そういうと、”コトリ”と電話の脇に受話器を置く音がした。しばらくして、ガサガサと何かを探る音が聞こえてくる。
『…あったぞ。なんだ、筆が進まないのをペンが無い所為にしようっていうのか?』
『そうや。それがないとイマイチ調子が出ぇへん』
彼は、アリスが小説を書く際に必ずそのペンを使用していることに気付いていたらしい。そのことにアリスは驚いた。
『それにしても、なんで俺のに入ってるんだ』
『キミ、次の教室が離れたとこやったから、移動するのにバタバタして片付けたやろ。そんときに混ざったんやないか』
『そうか?それはすまなかったな。 で、どうするんだコレ?まさか今から持って来いとは言わねえよな』
もしかしたら彼は気付いているのかもしれない、と思うと、アリスの心臓が僅かに跳ねた。
『いや、もう今日は書かんから。明日でええわ』
『ああ、わかった。じゃあ明日』
『よろしく。…おやすみ…』
ペンが火村の元にあることを、アリスは知っていた。
火村が見ていない隙に、彼のペンケースに自分のペンを忍ばせたのはほかの誰でもない、アリスだから。
夜になると無償に火村の声が聴きたくなるようになったのは、つい最近のこと。それならばすぐに電話をかければよいのだろうが、躊躇してしまう。大学に行けば会えるのだから、急用でもないのにわざわざ電話をかけるなんておかしいだろう。それに、火村の声が聴きたいからという理由を認めたくなくて。
用事があれば電話ができるのだと思ったアリスは、今日の行動に出たのだった。
「なんであんなことしたんやろ…」
聡い火村が、自分が仕掛けたことに気付かないはずがない。そうわかっていてもやってしまった。それほどまでに火村の声を聴きたかったのか。いや、声を聴いたら自分はどうなるのか、きっとそれが知りたかったのだ。
結果は—
「まだ11時か…」
今から毎日長い夜が続くのだろうと、アリスは漠然とわかっていた。なぜそう思ったのかは自分でもわからないのだが—
とりあえず明日は火村に会える。そう考え微笑みながらも、まだまだ眠れないであろう今夜はどうやって過ごそうかと思案する。
—夜の長さは 気持ちの深さ—
このことにアリスが気付くのは、まだ少し先のこと…
Fin