今、齢十二半ばの少年が路地裏で佇んでいる。少年の名はクルト・ヴェス。彼は一見普通の子供である。蜜色の髪と、眼鏡の奥の常盤の瞳がとても印象的であった。 人目に晒されぬ処で、この図形を描かれよ。
その一見普通の子供である彼が何故路地裏で佇んでいるのか。子供ならばそういうところで遊びたがるものだ、と思うかもしれない。或いは、訳あって路地裏に住んでいるのかもしれない、と思うかもしれない。それは間違いだ。決して路地裏に住んでいるのではない。彼は、制服であろう茶色の半ズボンに、私立小学校のエンブレムの付いた上着を着ている。裕福な家庭であるらしい。実は彼は今、ある人を待っているのだ。彼が此処に着いてからかれこれ一時間になる。
彼、クルトは十二歳とは思えないようなため息をついた。と、その時
「ごっめーんクルト」
と、いやに甘ったるい声と共に一人の少女がやってきた。彼女の名前はカタリーナ・エーベルト。クルトと同じエンブレムの付いた上着と茶色のプリーツスカートを身につけている。
「一時間4分二十五秒。…カタリーナ・エーベルト、君は幾つになったら時計が読めるようになるんだ?」
クルトはあきれ返ったような口調でカタリーナに遠回しの皮肉を吐いた。
その言葉に少しむっとしたカタリーナは、すぐさま言葉を返す。
「なにさクルト・ヴェス、十二にもなって時計が読めないなんてばかにしないでよ。私だって時計くらい読めるわ、…ただちょっと、家を出るのが遅かっただけよ」
カタリーナはふくれかえって栗色の長い髪を手ぐしでといた。
「…変わらないな、君も。小さい頃と全く一緒じゃないか。…もういい、この埒のあかない会話はもう止めよう。それより持ってきたかい、あれ」
クルトがそう言うと、カタリーナはにやっと笑い、
「あったり前じゃない。これが無かったら意味ないでしょ」
といった。そして鞄の中から、何やら暗色で絹張りの装丁が施されている、分厚い本を取りだした。表紙の金文字は、もはや擦り切れて読めなかった。二人は顔を見合わせて、その表紙を開いた。
頁を捲ると、こう書かれてあった。
そしてこの言葉を唱えられよ。
されば、道は開かれん。
汝がこの書を綴るのだ。
「…図形?」
二人はまたもや顔を見合わせた。その頁にも、後の頁にも、図形なんてものは一つも見あたらなかったのだから。
「図形を描け…って言われても…」
クルトが眉間に皺を寄せた。カタリーナは、本の頁を捲ってみたりひっくり返してみたりしていたが、手が滑って本を落としてしまった。本は裏表紙を向けた。
「あ」
カタリーナは小さな声を上げた。そこには、小指の先程の大きさでこんな図形が描かれてあった。
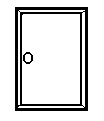
「…ドアみたいね」
「子供の落書きっぽいよね」
そしてクルトが次の言葉を発そうとしたその時、耳鳴りに似た音と共に本の一頁目が一瞬白い光を放った。
二人は慌てて本から数十センチ離れ、目を見開いてその本を見た。
「光った…」
「…」
言葉もなくぶんぶんと首を縦に振るカタリーナ。
クルトは本にゆっくり手を伸ばした。もうその本は光っていなかった。カタリーナは少し離れてクルトの様子を見ている。
クルトがさっきの頁を開くと、そこには
あたり。
この図形を描かれよ。
「…この本おかしい…ねぇクルト、絶対おかしいって」
カタリーナは大きな金茶の瞳を更に大きくして、クルトを見た。
だが、クルトは取り合わなかった。そして鞄の中から白墨を取りだして、
「このドアみたいなのを描けばいいんだろ?」
と言い、壁に描こうとした。
「ねぇ、クルト、何が起こるかわかんないよ?」
カタリーナはクルトの意を確かめるように問う。
「カタリーナ、それはもう覚悟の上だろ。もとはといえば、君がこの本の秘密が知りたいって言ったんじゃないか」
クルトはカタリーナに諭すような言い方をしているが、表情は心底楽しんでいるように見えた。
「それはまぁ…そうなんだけどぉ…」
カタリーナは渋っている。そうこう言っているうちに、簡単な図形は描き上がってしまった。
「よし、描けた」
とクルトが言い終わらない間に、先程同様本は唸りをあげ光を放った。
「…今度は何て描いてある?」
カタリーナは問うばかりで、決して自分で本を触ろうとはしない。クルトはそんな彼女を横目で身ながら、本を開く。
先程の文章の後には、
よろしい。
次はこの言葉を唱えられよ。
「我が書を綴る者。扉を開かれよ。」
…幸運を祈る
とあった。だが、その小さな文字は彼らに見つけられることはなかった。「ほら、カタリーナ。君もこっちに来て本持って」
クルトは彼女に本の左側(つまり表紙だけの軽い方)を持たせ、ドアの絵の前に立った。
そして、カタリーナに告げた。
「…カタリーナ、どうやらこれは本当に魔法の本のようだ———そして、もしここに書いてある通りの意味だとすれば———このドアの絵から別の世界へ行けるようになるみたいだ。もし、君が望まないのであれば、今すぐ止めても構わないけど、どうする?」
クルトの常盤の瞳は、何か挑戦するような色を浮かべていた。実際、彼はこの状況を心底楽しんでいて、カタリーナが嫌だといっても一人でやってしまいそうだった。カタリーナはクルトの常盤の瞳を見つめて、
「…いいわ、クルトに着いていってあげるわ」
と言った。その恩着せがましい言い方もいつまでたっても治らないね、とクルトは言いたかったが止めにした。あまり彼女をからかうと口も聞いてくれなくなるのを知っていたからだ。
「じゃあ、この本に書いてある呪文は僕が唱えよう。いいかい」
彼は息を吸うとゆっくりと唱え始めた———
「我が書を綴る者…扉を開かれよ」
次の瞬間、鏡に太陽光を当てたような明かりが辺り一面に広がり、その白墨で描かれた絵は重々しい色合いの、装飾があでやかな扉に姿を変えた。二人は目を丸くしてそれを見た。言葉も出ない。
その扉は、二人を迎え入れるように音もなく開いた。扉の向こうは白く光って見えない。
彼らは、取りあえず鞄を背負い、本の指示を待った。
…しばらく、待った。
「…これは…もうご勝手に、ということだろうか?」
クルトは本をぽんぽん叩きながら呟いた。
カタリーナは髪を手ぐしでときながら、
「じゃあ、何かの役に立つかもしれないから、この本持っていこうよ」
と、鞄を開けようとした。
すると本は拒絶するかのように強い光を放ち、風もないのにページがぱらぱら捲れた。開かれた頁には整然とした活字でこう書かれていた。
子は虚の世界に 我は実の世界に
彼の者達は実よりの使者
彼の者達が虚を創る
何を得て 何を捨て 何を失うか
理を得るだけが出口ではない
何を得るのも彼の者達次第
我は彼の者達を綴るのみ
言の葉のみで綴るだけ
「…意志を持つ本なんてな。やっぱりご勝手に、じゃないか」
二人とも思い思いの事を言ったあと、本を閉じて壁に立てかけて置いた。本は、——表紙を開いて弱く一回光り、ぱらぱらと頁を捲った。カタリーナは暫く本を見つめていたが、瞬きしたその時に本はぱたんと閉じ、地面の上に倒れた。そして、また弱々しく二回光り、本の上に小さな瓶が現れた。
「…?」
何のつもりかしら、とカタリーナは思った。その小瓶は注ぎ口の下の括れたところに桃色のリボンが結んであり、ラベルには『酔い覚まし』と書かれていた。中にはリボンと同じ桃色の液体が揺れていた。
「…酔い覚まし…?」
まるで訳が分からない。『酔い覚まし』なんて、必要としないのに!
「ねぇ、クルト。あの本が訳のわかんない瓶を出したんだけど」
カタリーナはクルトの目の前にずいっと瓶を突き出した。
「え?瓶?」
クルトは扉を触ったり、叩いたりしていた。彼はその扉の材質が知りたくてたまらないのだ。元はただの壁だったものがあっという間に重厚な扉になったのが面白くて仕方がなかったのだ。
クルトは目を細めて小瓶を見た。
「……『酔い覚まし』」
「ね?訳わかんないでしょう?」
「何でこんな物を出したのか、そこの本にでもお伺いを立ててみなよ」
クルトは素っ気なく返事をし、研究に戻った。
「もぅ……」
カタリーナはクルトが言ったとおり、本を手にとって開いてみた。
3頁目に文字が追加されていた。
『お餞別』だ。
遠い異国の昔話を知っているか?
初めは藁しか持っていなかった男が
莫大な富と妻を手に入れた話だ。
子よ、そなたも試してみるといい。
虚の世界で。
カタリーナは瞬きを数回繰り返した。
異国の話って…『藁しべ長者』のことかしら?——と、彼女は考えた。
「…取りあえず、持っておくことにするわ」
彼女は本に向かってそういい、本を閉じて壁に立てかけて置いた。そして、小瓶を背中の鞄にしまい込んだ。
「カタリーナッ!」
突然、クルトの鋭い声がした。
「どうしたの、クルト?——!大変!」
カタリーナは慌ててクルトのいる扉の方へ走った。扉はもうすでに三分の一くらい締まりかけていて、クルトは扉の向こうから懸命に腕を伸ばしてカタリーナを待っていた。
彼はいつの間にやら鞄をきちんと背負い、相貌を好奇心で輝かせていた。
「カタリーナ!早く、扉が閉まる」
「やっ、ちょ、ちょっと待ってぇ〜…きゃあ!」
カタリーナはクルトの手を取り、扉の向こうに倒れた。と同時に扉は音も立てずに締まり、本は今限りの光を出して頁を捲る。
開かれた頁には、文がひとつ。
『行ってらっしゃい、子供達』
本はその場に初めからなかったかのように、姿を消した。
